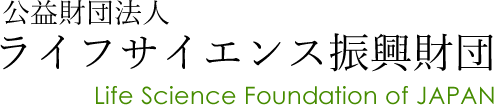第2回 国におけるライフサイエンスの位置づけ
仮想参加者(前回と同様)
S先生:文部科学省で長年、ライフサイエンスの行政や調査分析に携わってきている。
A君(男):スーパーサイエンスハイスクールの高校生。理科では生物を選択している。
Bさん(女):大学3年生。生物学科に所属し、専門課程で生物実験を始めている。
C氏(男):IT企業に勤めるエンジニア。
Dさん(女):子育て中の主婦。原子力や組換え食品に興味がある。
E氏(男):大企業(原子力関係)を退職し、現在は家でのんびりしている。
国がライフサイエンスを進める意義
S先生:皆さんこんにちは。第2回目の講義を始めます。今回は国におけるライフサイエンスの位置づけということで、少し硬い話になるかもしれませんが、よろしく。
A 君:僕は、あまり国がどうのこうのというのは興味ないんだけど、国の方針でライフサイエンスは違ってくるんですか。
S先生:そうだね。いいところに目をつけたね。皆さんはどう思いますか。ちょっと広く考えてみましょうか。ライフサイエンスはずっと、国の科学技術政策の一環として考えられてきました。では、日本の国は、科学技術を発達させる必要があるんでしょうか。またそれはなぜでしょうか。
Dさん:そもそも科学技術を発達させる必要ってあるのかしら。科学技術のせいで、環境問題や公害や、原子力爆弾や、遺伝子組換え食品の問題が起きてきたんじゃないの。
C 氏:おっとそんな根源的なことから言いますか。ヒトは二足歩行になって、手が自由に使えるようになると、火を使ったり道具を使ったりするようになって他の動物から区別されてきたと思います。私は、科学技術そのものは、人類が幸福になるのには欠かせないものだと思います。私のやっているITなんて最たるものですね。Dさんだって、スマホを使っているでしょ。今やそれがないと生活がすごく不便になるんじゃないですか。
Dさん:あらそうだわね。まあ確かに、科学技術があるっていうのは便利なものだけど…
Bさん:私も科学技術を発達させていくことに賛成。生物の実験をやっていて、この研究がいつか役に立てばいいなあと思っています。いろんな医薬品は人類の病気を治し、寿命を延ばすのに役立ってきたと思います。
S先生:Dさんの言うように、科学技術には確かに負の面があると思います。ライフサイエンスでも、Dさんのいうような遺伝子組換え食品で体に害のあるものが出回るかもしれないし、それから、遺伝子組換え技術を悪用して危険なウイルスを作ったり、漏れたりといったこともあると思います。だからこそ、そういったことにならないように、科学技術に対してもしっかりした規制を行わないといけないし、それから、まさに科学技術を利用して、被害を食い止めることも必要ですね。こうしたことはまた別の機会を設けてお話しさせてもらいますね。ところで、日本は特に、他の国と比べて科学技術を発達させなければならない理由はあるでしょうか。
E 氏:そりゃ、日本は何も持っているものがないからね。ロシアやカナダのように広い土地はない。山が多くて平野が少ないから、アメリカのように大規模な農業もやりにくい。石油や石炭のようなエネルギーも、鉄や銅のような資源もとれない。そんな中で、たくさんの人口を抱えて、その人たちがある程度豊かで文化的な生活を送るためには、科学技術を使って生活を豊かにしないといけない。科学技術をどんどん発達させて、海外にできた製品を輸出して儲けないと、1億人もの日本の国民を養っていけないからね。私はずっと原子力産業で働いてけど、昔から、資源やエネルギー源の少ない日本は、何とかしてエネルギーを増やすために国を挙げて原子力の推進に取り組んできていたよ。国から研究開発のためにいっぱいお金が出されているし、安全規制なんかも国が法律に則って行ってきた。だから、少なくとも原子力については、国の方針で大きく進め方が違ってくると思う。
S先生:ありがとうございます。私が説明しようとしていたことを言ってもらえました。
ライフサイエンスは他の科学技術と違うのか
C 氏:でも、原子力とライフサイエンスではちょっと違っているような気もします。原子力のような大きなプラントをつくるとなると、しかもそのプラントのために大勢の人たちが働いていると、方向づけも必要かもしれないけど、ライフサイエンスって、どうも研究室でちまちまやっているようなイメージがありますから、国がどれだけ必要なのかわかりません。私のようなIT分野だと、確かにスパコン開発なんかは大きな費用がかかりますが、ITを利用して新しい商売や事業を行うのは、国の助けを借りずに、個人がアイデアで勝負して、そのアイデアが良ければ、国の助けを借りなくても個人で事業を伸ばしていける場合も多いかも。
S先生:そうですね。国のかかわりというのは、分野によっても、また、事業の大きさによっても違うかもしれませんね。ライフサイエンスについてはどうかというと、Cさんの言うように、少し前まではちまちまやっているイメージがあったと思います。でも、それじゃあ国は金は出す必要はないかというと、どうでしょうか。国がお金を出さない場合は誰が出すんでしょう。
Bさん:その場合は、企業でしょうか。
S先生:そうですね。Bさんの言うように、日本にはトヨタとかソニーとか、大きな企業がいっぱいあります。ライフサイエンスにしても、まずまず大きな製薬会社があります。実際には日本の国は、科学技術に対しては国は民間ほどお金を出していません。民間企業が率先して、自らお金をかけて研究を行っています。だから日本の国はある程度、競争力を維持しているんです。もっとも最近は別の理由もあって、なかなか競争力を維持し続けることが難しくなっているのですが。
Bさん:でも、企業がお金を出すのは儲けが期待できる研究に限られているから、あまり自由な発想での研究は行えないような気がします。
S先生:そうですね。企業も自分たちの得意な分野で改良していくためにはお金を出しますが、まったく新しいことにはなかなかお金を出そうとはしません。でも、新しい技術の芽や産業の芽がなければ、そもそも技術や産業は発達しません。まったく新しいところにこそ、将来的に大きな分野になる、すぐれた発見のもとが転がっているのです。でも、それは個々の企業ではしっかりできないので、国が税金の中からある程度のお金を用いて、大学とか、国の研究所とか、あるいは企業にも、基礎研究や、基盤となるような研究を行わせる必要が出てくるのです。
C 氏:なるほど分かりました。個人の発想によるような小さなものでも、儲かるかどうか分からないようなものには企業がお金を出してくれないから、国が率先してお金を出す必要があるということですね。そうすると、ライフサイエンスはそんな研究が多いから、お金を出す必要があるということですか。
S先生:まあそうですね。ライフサイエンスは、対象となる生物の種類とか、実験系が実に多くて、基礎研究に位置付けられるものが多いですが、だからこそ、そのようなさまざまな研究の中から、すごく役に立つものが生まれる可能性があります。国がお金を出す意義もあると思いますね。
A 君:えっと、ライフサイエンスには原子力のようなビッグプロジェクトってないんですか。
S先生:おっ、いい質問だね。ちまちまやっていると言いましたが、ただ、そんな研究だけではないですね。研究機関同士が協力したり、さらには海外と協力したりして行う、いわゆるビッグプロジェクトもずいぶん増えてきました。そのようにして得た成果が、プラットフォームすなわち研究基盤やデータの基盤となって、いろいろなところで役に立つという場合も出てきます。これは基礎研究というより、基盤研究といったらいいかもしれませんが、そうなると、一企業ではとうていお金が出せないけれど、国として進めていく意義は大いにあると思うんですよ。
Dさん:なんか、むずかしい話になってきたわね。なんとなく言っていることは分かるけど、ライフサイエンスで実際にそんな、国が関わるような大きなプロジェクトがあるのかしら。
S先生: ありますよ。決してスパコンとか原子炉とか望遠鏡の開発のように装置自体が大きいものじゃないけど、たとえばゲノムやその他の生体物質を全部調べて、解析したりするものとか、生物や病気などの情報をデータベース化して誰でも使えるようにするとか、脳や免疫などの仕組みを体系的に調べていくことなどは、とても多くの資金や労力が必要になるので、国が音頭をとって進めていかないといけなくなってきていますよ。
Dさん:えっと、難しくなってきたわね。話の腰を折って申し訳ないんだけど、ゲノムって何なの?よく聞く言葉だけど。
A 君:それは僕はこの前生物の授業で習いました。ゲノムって、生物の身体の設計図のうち、必要最小限の1セットのことだったと思います。たとえばヒトの場合は、一つの細胞の中に46本の染色体があるけど、そのうち22本については同じものが2つずつあって、22×2=44本、あと2本はX染色体とY染色体になっています。だから22本+XY染色体の計24本の染色体をゲノムといいます。
S先生:すばらしいっ、上手に言えたね。そうだね~このことについては、また別の機会を設けてまとめて話をしますね。それでは元に戻って。とにかく、日本の国としては、科学技術を進めていく必要があるということで、皆さんの認識はよろしいですか。
一 同:はい。
科学技術基本法と科学技術基本計画
S先生:幸いにも日本人は昔からものづくりは得意で、知識をきちんと身につけてどんどん改良していくことのできる器用な民族です。だから昔から、日本の得意な科学技術をもっともっと伸ばして、日本の国を豊かにしていこうということが、国の政策になっていました。でも、今から20年前、1995年に、それがはっきりした形になりました。何だと思いますか。
Bさん:まだ私が生まれる前のことですから、分かりません。確かその年には阪神大震災やオウム事件などがあったから特別な年というイメージがあるのですが、それと関係があるんですか。
S先生:うう~ん。直接は関係ないですが、まあ、その頃の時代の雰囲気とは関係していますね。
Dさん:ノストラダムスの大予言とか。でもあれはもっと後。1997年7月だったわね。
S先生:いや~違います。でも暗い雰囲気というと、ちょっと近いかも。
E 氏:原子力では、その年にはもんじゅの事故があったなあ。あれは我々原子力業界の者にとっては衝撃的だった。メディア対応などを誤ったばっかりに、原子力政策が大きく遅れることになったな。
C 氏:わかりました。日本の経済の停滞ですね。まだ私は子供でしたけど、株価がどんどん落ちて、バブルがはじけて日本の企業もつぶれるところがいっぱいでてきた。いわゆる、「失われた10年」の真っただ中だ。
S先生:そのとおりです。それまで破竹の勢いで世界をリードしてきた日本の経済に陰りが出てきて、その陰りがどんどん大きくなっていました。そこで、それを打破しないといけないと、国会議員さんたちが立ち上がったんです。
Dさん:へえっ。科学技術と議員さんって、あまり結びつかないわね。よく農水族とか建設族とかっていうのは聞いたことがあるけど。
S先生:科学技術の推進については、異論をはさむような議員さんはいません。ただDさんがおっしゃるような、いわゆる利益誘導型の族議員というのは、おそらく科学技術に関してはいないと思います。それでも、科学技術の重要性を認識してくれる議員さんが何人かいて、いわゆる超党派、つまり党を超えて協力し、科学技術を推進するための基本法を作ろうという機運が盛り上がりました。そうして1995年、科学技術基本法という法律が制定されたんです。何とか科学技術の力で、日本の将来を豊かなものにしていこう、そう考えて、科学技術を推進するための基本法を作ったんです。

Cさん:へえっ、知りませんでした。あまり法律には詳しくないもんですから。いったいどんな内容なんですか。
S先生:そうですね。この法律の中で一番大切な内容は、科学技術基本計画というものを5年毎に作って、その5年間の間に日本の科学技術を進めていくための目標を定めるということです。そして、その目標を達成するために必要な予算も出させるということです。
Dさん:出させるって、いったいどこから??
S先生:あはは。ついつい役人の癖が出てしまいました。国の仕事は、国民や企業などから得た税金を使って行われていますよね。だから、そのお金を使えばいいのですが、自由に使えるわけではありません。国には他にも、社会保障費とか、防衛費とか、国債の返還とか、公共事業費とか、必要なことにお金を使わなければなりません。だから、科学技術を進めようとするなら、それを進めるためには、各省庁は、その意義を一つ一つ、国の予算の管理を行っている財務省に説明しなければなりません。その時に、もし、5年間の基本計画の間に、科学技術にこれだけの予算を出すんだと決めておけば、それほど苦労しなくても予算をとることができるだろうと考えたわけですね。

Dさん:へえっ。なんか役人って、頭がいいというか、ズルいというか・・・・。
S先生:いや。科学技術基本法や科学技術基本計画を作ったのは役人ではなくて、超党派の議員さんたちの働きが大きかったと思いますよ。それに、予算は役所だけで決められるんじゃなくって、最後に国会で議員さんたちに承認してもらわなければならないですからね。もちろん役人たちは、一生懸命、そのための準備や、下働きをしているんですけどね。
A 君:ああ、そうだったですね。中学校の時に習いました。予算の承認というのは、政府の作った原案を衆議院と参議院で審議し、承認するんですね。参議院で否決されても、衆議院でもう一度承認されたら通過する・・・。
S先生:そうですね。よく覚えていましたね。役人は1年間、そうした通常の予算とか、追加で編成される補正予算とかで、資料作りやいろいろな所への説明なんかが結構大変なんですよね。だから、そうした時に、科学技術予算については、国の方針としてこうなっているからそのための予算をつけるように、と裏付けてくれる根拠があると、すごくありがたいんですよ。
E 氏:う~ん。何となくわかるなあ。上杉鷹山だったっけ。江戸時代の大名だったけど、財政が厳しい時こそ、人を育てることが大切と、なけなしのお金をはたいて学問所を作って、技術や産業を振興して、そのおかげで彼の藩は飢饉なども無事乗り越えたって聞いことがある。
Dさん:へえっ。昔にも立派な考えを持った人がいたのね。私なんか、主婦としては、お金があったら少しでも消費税を下げたり、お金を配ったりして、私たちの生活をちょっとでも楽にしてもらいたいと思うんだけど。
競争的資金の導入
S先生:はいっ、じゃあとにかく、科学技術基本法と基本計画に戻りますね。とにかく、このようにして、科学技術基本法が、そしてそれに基づき、5年間の計画が定期的に作られてきました。それに沿って、いろいろな目標が掲げられました。ここでは特徴になるようなものを抜き出しておきます。これについては全部説明するつもりはありません。全部説明すると、全く時間が足りなくなります。ですが、少しだけ。
たとえば「競争的資金の拡充」。以前は大学や研究機関に対して、何も言わなくてもその規模や職員の数に応じて、一定のお金が国から拠出されていました。大学や研究所ではそのお金を使って自分たちのやりたい研究をしていました。しかし、それでは研究者がお金の上にあぐらをかいて、ちんたらちんたらとしか研究しないかもしれない。ならば、そのように一定額で出される研究費を減らして、その減らした額に見合うようなお金をグラント、すなわち懸賞のような形で研究者に応募させて、採択された者にだけ研究費を出すという形にしたわけです。結構厳しいですよね。そうしてどんどん各大学に無条件で出されるお金は減っていって、その代わりに競争で獲得させるお金は増やしていきました。弱肉強食ですね。各大学や研究者は生き残りをかけて壮絶な競争をする時代になったのです。

Bさん:そうそう。私の大学でも、教授や准教授の先生方は、自由に使えるお金が無くなって、困った、困ったと言っています。いっぱい研究費をとれる先生と、そうでない先生が出てきたので、結構研究室によって貧富の差が出てきているようですよ。
E 氏:そうなんだ。そんなことでいいのかなあ。まあ私のいた原子力の世界は、エネルギー対策特別会計のように、結構自由に使えるお金があったから、ゆとりがあったかな。おっと、あまりそんなことを言っちゃいけないかな。それに、原子力は個人のアイデアで進めるようなものじゃあないから、競争的資金にはあまり向いていないかな。まあほんとにプラント作りの段階になると電力会社がお金を出すからね。ライフサイエンス分野はそれに比べて大変だな。
C 氏:そうですね。私のようなIT分野だと個人のアイデアベースになるところが多いけど、そこまでお金はかからないかもしれないですね。
S先生:はいはい。皆さんありがとうございます。Bさんの言われたように研究室にゆとりがなくなり、自由な研究ができなくなったというのは、競争的資金へのシフトのひとつの弊害とされています。また、Eさんのような原子力の世界でも、私がかつて担当していたような放射線研究の分野では結構細かい、個人ベースのアイデアもありました。またCさんの言われるITの分野でも、スパコンなどを作ったりする場合は巨大な予算が必要になりますね。まあ、分野によって、基礎研究、基盤研究と応用研究、実用化研究の割合は異なりますが、いろいろな側面がありますね。
ポスドク問題
S先生:ちょっと話を進めます。Bさんには関係しているかもしれませんが、第一期の基本計画では、ポスドク1万人拡充計画というのがとられました。ポスドクというのは何の略か知っていますか。
Bさん:はい、もちろん。ポストドクター、つまり博士課程を修了した人たちという意味ですね。
S先生:そう。日本で研究者になるためには、普通の学部の場合、まず大学で4年間を終えた後、大学院に行きます。そこで修士課程―マスターコースといいますが、そこで2年間研究します。そしてその後、博士課程―ドクターコースで3年間研究します。そうすると、うまくいけば学位がもらえます。つまり、大学と修士課程と博士課程を合計して、最低9年間は大学にいないと研究者にはなれないのです。そして博士課程を終えた人たちはポストドクターすなわちポスドクになるわけです。ポスドクは立派な研究者ですが、研究者としてのスキルアップを図るために、さらにいろんな研究機関で任期付きで3年くらいずつ勤めて、その後、正規の職員として雇われて、やっと一人前になれるのです。このポスドク一万人計画というのは、このポスドクの数をもっと増やして、日本の研究活動をもっともっと活発にしようという計画でした。
Dさん:へえっ、研究者になるのって、そんなに大変なの。すぐに就職させてあげればいいのに。
S先生:ちょっと考えるとそう思う人が多いと思います。でも、一人前の研究者にとっては、これは必要な過程だと思います。ポスドク期間のうちにいろいろな分野や研究方法をマスターすることで、ノウハウを身につけていく。まあお医者さんの場合の医療実習に似たような位置づけですかね。いわゆる武者修行です。
Bさん:でも、ポスドクの人たちは安定した就職先を見つけるために、結構苦労しているって聞いています。ほんとにそんな計画がよかったのかどうか、私にはよく分かりません。
E 氏:私の若い頃には、オーバードクター問題って言うのがあったけど、それとは違うのかな。
S先生:そうですね。昔は確かにオーバードクター問題というのがありましたね。それは博士課程を取得して最初の就職先がなかなか見つからないという問題です。Bさんの言うようなポスドク問題というのは、博士課程を出た後、ポスドクにはなれても、任期付きで不安定で、なかなかテニュアという、永久就職ができないということですね。これについては、またそのうち、ライフサイエンス人材ということで、まとめて取り上げて議論させてもらいますね。Bさんいいですか。
Bさん:はい。必ずお願いします。
ノーベル賞50年間で30人
S先生:それでは、これ以外のもの。第二期の基本計画には、面白い計画が盛り込まれました。それは、今後50年間で30人以上ノーベル賞をとらせようという計画でした。ところで皆さんは、ノーベル賞受賞者の名前を言えますか。全部言えと言われても言えないでしょう。テレビのクイズの問題に出されるくらいでしょうから。
E 氏:う~む。昔の数が少ない時だったら言えたんだけどなあ。湯川秀樹、朝永振一郎、川端康成・・・ノーベル賞をもらうととてつもなく頭のいい人というイメージがあった。
S先生:A君はどうですか。
A 君:え~と。iPS細胞を作った山中先生くらいしか知りません。
Dさん:あら。山中先生は私が言おうと思っていたのに、残念。じゃあ、文学好きの主婦としては、大江健三郎先生を挙げさせてもらうわ。あと、イシグロ・カズオさんも。「私を離さないで」っていう彼の小説が日本でドラマされて、それを見ていたから。
Bさん:私は、生命科学の分野はまあまあ知っているけど、山中先生以外だと、免疫の遺伝子再構成のしくみを発見した利根川先生、感染症の治療法を開発してアフリカで多くの人たちを助けた大村先生、それからがんの特効薬を発明した本庶先生などを覚えています。

S先生:はい。ありがとうございます。ノーベル賞の日本人受賞者の数は、文学賞や平和賞も含めて28人もいます。国籍を変えたりしている人もいるので少し数が変動するのですが。こんなに多いとなかなか全員を言えるわけはないですね。
でも、第二期基本計画になる前、20世紀にはノーベル賞を取った日本人はほとんどいなかった。それこそ、10年に1度くらいしか出なかったので、Eさんの言われるように、みんなが名前を言えた。だからそんな時に、50年間に30人という数字を見て、多くの人々はびっくりしたわけです。絵に描いた餅だろうって。
しかし、その後、ノーベル賞受賞者が増産されました。このままのペースでいけば、この50年間に30人という目標もクリアされそうな勢いです。ただ、現在もらっている人たちは、科学技術基本法ができるよりずっと前の成果が評価されて受賞した人がほとんどです。だから今後はどうなるか分からないですね。
なお、このうちライフサイエンス分野は、さきほどBさんが挙げられた先生方以外に、大隅先生がいます。大隅先生は、私が東大の学部の時の先輩にあたりますが、生物の体にできた老廃物、つまりゴミを処理する仕組みを発見したということで、とてもユニークな発見をしました。

Bさん:あっそうか、忘れていました。そうすると、ライフサイエンス分野でノーベル賞をもらったのは全部で5人ということですか。
S先生:ノーベル生理学・医学賞ということなら5人ですが、ライフサイエンスということで考えると、そのほかに、ノーベル化学賞をもらった下村先生がいます。オワンクラゲから蛍光を発する遺伝子を抽出して、いろいろな生物の実験に標識として使われるようにした先生ですね。
Dさん:ああ、そういえば実験するためにクラゲをいっぱい海でとって集めたっていうのが昔、ニュースで流れていたのを見たことがあるわ。
S先生:さて、はたしてこのペースでノーベル賞受賞が続くのかどうか。ちょっと心配な要素も出てきていますが、それについてはまたの機会にして。
科学技術予算は増大したか
S先生:話を戻して科学技術基本計画ですが、これまで6回、作られてきています。今は第六期の基本計画の期間になっています。さて、それぞれの期の基本計画には、最初に説明させてもらったように、それぞれの期間の間の予算額の目標を立てました。そして、それを目標にして予算の交渉が行われました。結果はどうだったでしょうか。
Cさん:えっ、計画通りにいったんじゃないんですか。
S先生:実は、なかなか思惑通りにはいきませんでした。第一期は目標17兆円に対して実績17.6兆円、第二期は目標21兆円に対して実績21.1兆円と、ここまでは何とかぎりぎりで目標を達成することができました。でもその後は、第三期は目標24兆円に対して21.7兆円、第四期は目標25兆円に対して実績が22.9兆円と下回りました。

Cさん:ふうん。それって、ない袖は振れないって言うことなの。
S先生:まあ、そんなこともありますね。でも、第五期は目標26兆円に対して28.6兆円と、久々に上回りました。
E 氏:そうなんだ。とにかく目標通りでなくても、そんなに下回らなかったこと自体はすごいな。確かその頃は、不景気でもあったし、国の予算自体も伸び悩んでいたんじゃなかったかな。
S先生:はは、失われた10年の真っただ中ですからね。だから政府全体の予算があまり伸びていない中で、科学技術にそれだけの額が配分されてきたのは、まずまず立派だと思います。
さて、科学技術基本計画の中では、科学技術の中でメリハリをつけようとして、重点的に推進していく分野が決められた時もありました。
第二期基本計画では「ライフサイエンス」、「情報通信」、「環境」、「ナノテク・材料」の4分野が重点分野に指定されました。この4分野は続く第三期基本計画でも重点推進分野に指定されました。そしてさらに、第四期基本計画では、「ライフイノベーション」と「グリーンイノベーション」の2つに重点を置くことになりました。ところが皆さん、第一回の講義で説明しましたように、「環境」という分野は、実は、広い意味ではライフサイエンスに含まれているのです。要は、重点事項は全てライフサイエンスということ。
まあこれは言い過ぎかもしれません。実際にはグリーンイノベーションの大部分はエネルギー関係になっていました。

C 氏:へえっ、ライフサイエンスって国にとってそんなに重要なんだ。でもITで飯を食べている私としては、今の状態がどんなものか知りたいですね。やっぱりITやAIがすごく発達してきているから、そっちの方が中心になってきているのでは? 第五期や第六期の基本計画ではどう位置付けられているんですか。
S先生:残念ながら? 第五期以降は、重点分野がどれだと明確に指定されることはなくなっています。科学技術はどの分野も全部大切だから、特定の分野だけに偏るのもよくないという考えでしょうか。すみません。私も分かりません。
健康・医療戦略推進法
S先生:しかし、ライフサイエンスに関しては、もっと大きな動きがありました。第五期の基本計画が策定される少し前、2014年のことですが、健康・医療戦略推進法という法律が制定されました。そしてそれに基づいて、医療分野研究開発推進計画というものが、やはり5年毎に作られることになったのです。だから、ライフサイエンスの中心である医療の分野の研究については、そちらの計画の方針に則って計画的にやっていこうということになったのです。

E 氏:そうか、そんなことがあったんだ。じゃあ、科学技術基本計画は、ライフサイエンスについてはがらんどうのような状態になってしまったということかな。
S先生:もちろん、農業・環境・工業等の他の分野も含めて、基本計画でライフサイエンス全般を推進していくという考え自体は変わりませんが、医療研究の推進は、医療分野研究開発基本計画で面倒をみるということですね。これについては重要な問題ですので、また別の機会にきちんとお話ししますね。それでは本日の講義はこれでおしまいにします。
一 同:ありがとうございました。
(第2回講義 了)
公益財団法人ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔