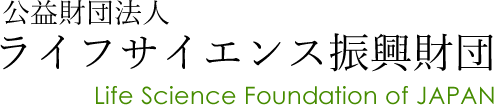第1回 ライフサイエンスとは?
仮想参加者
S先生:文部科学省で長年、ライフサイエンスの行政や調査分析に携わってきている。
A君(男):スーパーサイエンスハイスクールの高校生。理科では生物を選択している。
Bさん(女):大学3年生。生物学科に所属し、専門課程で生物実験を始めている。
C氏(男):IT企業に勤めるエンジニア。
Dさん(女):子育て中の主婦。原子力や組換え食品に興味がある。
E氏(男):大企業(原子力関係)を退職し、現在は家でのんびりしている。
自己紹介
S先生:皆さんこんにちは。これからはじめての講義を行います。
まず私の自己紹介をしますね。私は大学院で生命科学を専攻した後、今から40年も前、現在の文部科学省の前身である科学技術庁に入庁しました。その後、いろいろな省庁や自治体、研究所等で働きましたが、その中で、ライフサイエンスに関するさまざまな業務を経験して、自分で言うのもなんですが、けっこう幅広い知識を身につけてきました。
そんな私ですが、この講義を通して、参加者の皆さんの一人一人に、ライフイエンスの面白さを知ってもらうとともに、ライフサイエンスについて自分なりの考え方を養ってもらおうと願っています。
これから何回になるか分かりませんが、毎回、特定のテーマを設け、皆さんに、それぞれのテーマについて議論してもらいます。皆さんには議論にあたっては、ぜひ自分の頭で考えてもらいたいと思います。それではよろしくお願いします。ここまでで何か質問はありますか。
C 氏:私はあるIT企業に勤めています。ふだんはコンピュータ相手で、高校でも生物を選択しなかったため、ほとんど生物の基礎知識がないのですが、大丈夫でしょうか。
S先生:もちろん大丈夫です。議論に際して必要な基礎知識は、最初に私から提供しますし、もし議論の中で難しい言葉が出てきたら、その都度説明させてもらいます。一方で、ライフサイエンス分野にもITが使われてきています。逆にCさんに教えていただくこともあろうかと思います。その時はよろしくお願いしますね。
Dさん:私は主婦なので、生活のことにはけっこう敏感だけど、あまり難しい話になるとついていけないわ。実は組換え食品などのことは気になっているんだけど、本当に安全なのかどうなのか分からないので、教えてもらいたいのよ。そんなことも、この講義のテーマになるのかしら?
S先生:もちろんです。Dさんのような方が、主婦の目線、母親としての目線から率直にお話ししていただければ、議論も盛り上がると思いますよ。
A 君:僕はこの中では最年少になると思いますが、学校で生物の授業を聞いていて、とても面白いです。でも、けっこう覚えることが多くて多くて大変です。なんとか面白く生物を勉強していけたらうれしいです。
S先生:ありがとう。学校の勉強も忙しいのに、よくこの講義に参加してくれたね。A君の言うように、生物の分野はどんどん新しい発見がなされて興味深いのだけど、そのために、学ぶ量が多すぎるという問題も出てきているよ。またこれについても議論しようね。
Bさん:私は生命科学の知識はこの中では比較的ある方かもしれないけど、まだまだ知らないことがいっぱいあります。大学ではいろいろな実験をさせてもらって楽しいです。将来はぜひ、研究者になりたいのですが、博士課程まで行くとなかなか就職は厳しそうだし、特に女の場合は結婚や出産もあるから、研究者になるのはどうなのか、ちょっと悩んでいます。
S先生:そうですね。研究者のキャリアパスは、かなり前から問題になっていました。それから、女性研究者の問題は、一般の女性労働者のキャリアパスと同様、考えていかねばなりません。そういうことも、またお話しさせてもらいますね。
E 氏:私はずっと原子力産業で働いていて、今年退職したばかり。先生と同じ世代だけれど、ちょっと時間ができたので全く違う分野のことも知りたくなって、今回の講義に参加させてもらいました。一からライフサイエンスについて教えてもらえるというので、とてもワクワクしていますよ。皆さんよろしく。
S先生:そうですか。Eさんは私と同じ世代なのですね。でも、退職後もそうして新しい分野にチャレンジするのは、立派ですね。私もうれしいですよ。逆に私も原子力やエネルギーのことは知りたいし、いろいろ教えてくださいね。
ライフサイエンスのイメージ
S先生:さて、皆さんからの自己紹介や質問などを伺うと、皆さんそれぞれがライフサイエンスについて、既に自分なりのイメージを持っているように思えます。ライフサイエンスって、いったい何でしょうか。それぞれがイメージすることを話してください。A君はどうですか。
A 君:僕はまだ生物を勉強しはじめたばかりだから、あまり分からないけど、学校で学ぶ生物のことかなあと思います。でもライフサイエンスは、それよりももっと広い範囲になるんじゃないですか。
S先生:そうですね。ライフサイエンスは、学問としての生物学とは強く関係していると思いますよ。ではBさんは?
Bさん:私は、大学で生命科学を勉強しているので、ライフサイエンスとは生命科学のことかなあと思います。ライフは生命、科学はサイエンスですよね。まあイメージとしては、人の命を救うための科学ということかなあと。
S先生:そうか。Bさんとしては、生命科学、特に医療の世界に役立つような学問というイメージですかね。なお、生命科学は、正確にはライフサイエンスではなくて、バイオサイエンスと呼ぶのが一般的です。ライフサイエンスはそれとは少しニュアンスが異なるかもしれませんね。
Dさん:さっき私が言った、遺伝子組換え食品などもライフサイエンスに入るのかしら。ライフって、生活に密着したようなイメージがあるから。
S先生:そうですね。いいところに目をつけましたね。正解に近づいてきました。
E 氏:そうか。それを言うなら、私が専門としていた原子力は、いろんな分野で使われているけど、放射線治療なんかで医療に使われているし、放射線を使って品種改良もやっている。でも、それもDさんの言った遺伝子組換え食品と同じく、安全性について取りざたされることが多い。
S先生:そうですね。いい視点ですね。ライフサイエンスと安全性の問題については、また別のところでまとめて議論したいですね。
C 氏:原子力と関係があると言うなら、ITとだって関係あると思いますよ。つまり、コンピュータ、さらにAIなんかは、ヒトの脳の仕組みと関係が深いし、ディープラーニングなんかは、ヒトの脳を参考にしてつくられたものだから。
S先生:すばらしい。いいですね~。脳というのは、ライフサイエンス研究に残された最後のフロンティアだと言われています。脳の仕組みがAIに活かされるし、また、AIやITを使うことによって、さらにライフサイエンスの研究がより進化したものになることが期待されます。
ライフサイエンスの定義
S先生:皆さん、ライフサイエンスについて、イメージを膨らませてくれて嬉しいです。それぞれが抱いているライフサイエンスのイメージは、様々だろうと思いますが、そもそも、ライフサイエンスに似たような言葉はいろいろありますね。
E 氏:そうそう、私にとっては、ライフサイエンスより、バイオテクノロジーの方が、なじみが深い。でも、違う言葉なのでしょう。重なっているところもありそうだな。
Bさん:そういえば、私の研究室でいろんな学会に参加しているけど、日本生化学会と日本分子生物学会が2大学会だって先輩から教わりました。成果をどちらの学会で発表するかで迷う場合もあるとのことだから、生化学と分子生物学という用語も結構近いかもしれない。
S先生:そうですね。それではそろそろ、皆さんの御意見も踏まえつつ、情報を提供させてもらいますね。まず、この図を見てください。

S先生:この中には、さっきEさんが言ったバイオテクノロジーや、Dさんが言った生化学や分子生物学も含まれています。ライフサイエンスに関係している用語って、実に多いですね。でも、よく見てください。下の方は、学問的な気がするけど、上の方はどうでしょうか。
Dさん:上の方は横文字が多いわね。でも、バイオテクノロジー以外はあまり聞いたことがないわ。
S先生:そうですね。あまり業界でしか使わないような用語も混じっているんです。ライフサイエンスはまだまだ発展している分野だから、新しい用語をつけて、それぞれの分野を広げていこうという動きが結構あるんですよ。そうですね~この中には20年前には全く使われていなかった言葉もたくさんありますよ。でも、ライフサイエンスは、これらの言葉とは違って、日本の国としては、昔からライフサイエンスを定義しているんですよ。次の図を見てください。

S先生:私が科学技術庁に入ったのは昭和60年(1985年)で、今から40年も前の話です。でも、その頃には既に、ライフサイエンスという言葉はあったんです。A君、これを声に出して読んでくれるかな。
A 君:はい。 「ライフサイエンスとは、各種の生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明し、その研究成果を保健医療、環境保全、農業生産、工業生産等の諸分野において、人間生活に関わる諸問題の解決に役立てようとするものであり、大きな技術発展の可能性を持つものとして期待されている。」
S先生:皆さん、分かりましたか。つまり、「生命現象の解明」という基礎的な部分と「その成果を各分野に利用していく」という応用・実用化の部分と、両方からなるということです。だからこそ、ライフサイエンスは他の用語と違って、実に広範な分野をカバーしているんですよ。つまりこうです。

ライフサイエンス関係の学会
S先生:ほらっ、こんな風に、ライフサイエンスの世界はで、広がっているんです。
で、ここからちょっと雑談です。まさによもやま話だけど。
さっきBさんが言った、分子生物学と生化学の違いを一言で説明するのは難しいけど、でも、重なっている部分もあるし、独自の部分もある。結局、新しい分野が生まれてくると、その言葉を冠した学会が生まれるんです。ここには書いていないけど、日本ゲノム編集学会とか、日本再生医療学会とか、まだできて10年か20年くらいしか経っていない学会も多いですよ。でもそうして名前をつけ、学会とすることによって、同じような分野の人たちが集まって来て、ますますその分野が発展していくというメリットはありますよ。
E 氏:へえっ、そうなんだ。私は原子力のことしか分からんけれど、原子力はちょっと停滞していると思う。それでも廃炉とか、炉の寿命延長とか、新型炉とか、考えないといけないこともあって、学会の中でも動きはある。けれど、ライフサイエンスのように、こんなにいっぱい用語があって、それに応じた学会があるというのはちょっと想像がつかないな。なんか弊害のようなものはないのかな。
S先生:弊害になるかどうか分かりませんが、最近は、研究者の減少に加えて、新しい学会が生まれているから、会員数が減少して運営が苦しくなっているところもあるかもしれませんね。
C 氏:それなら、似たような学会を統合すればいいんじゃないですか。それに、学会を開くとお金がかかるから、リモートで学会を開くようにしたらいいでしょ。私の会社なんか、会議はほとんどがリモートですよ。
S先生:そうですね。コロナの時は、ライフサイエンス関係の学会もリモートで開くところが結構ありました。でもコロナが終わったら、その後はまた実際の会場を使って開催する場合が増えています。やっぱり、いろいろな人と面と向かって話ができるというのは、リモートでは得られない魅力ですからね。
Bさん:それに、私としては、学会に参加していろいろな所に行けるのは楽しみだから。
Dさん:わあ、いいなあ。私も行ってみたいな。京都なんかないのかな。
S先生:ありますよ。京都にも立派な会場がある。さっきの日本分子生物学会と日本生化学会の話ですが、両学会はBさんの言うようによく分野が似ているから、少し前は一年おきに、合同で開催していました。そんな時は、会場は特別大きくないといけないので、神戸とか横浜とか幕張とか福岡といった、大きな会場があるところに限定されましたけどね。
E 氏:そうか。合同開催の方が合理的なんでしょうな。でも最近はそれがされていないんですな。うまくいかなかったのかな。
S先生:私は正確なところは分かりません。でも学会にはそれぞれの風土があるので、たとえ合同開催はできても、学会どうしを統合するのはさらにハードルが一つ上がるでしょうね。
Eさん:うんうん、よく分かる。
S先生:学会のことについては、ホントはいろいろエグい話も知っているのですが、ちょっと本筋から外れていってしまうので、今回はここまでにしておきますね。
ライフサイエンスの各分野
S先生:さて、今回はあくまで導入ということで、もう少しだけライフサイエンス全般の話をさせてもらって終わりにしますね。さて、ライフサイエンスは各分野への応用があるということですが、それぞれどんなものがあるでしょうか。次の図を見てください。

S先生:ほらっ、いろんな分野に使われていますね。ところで、保健医療とか、農業生産とか、環境保全はライフサイエンスとつながりが深いっていうのはすぐに分かると思いますが、工業生産っていうのは何だと思いますか。A君分かるかな。
A 君:えっと、分かりません。何でしょうか。
E 氏:こりゃ、原子力か?でも違うだろうな。放射線利用だったらともかく、でも工業生産となると・・・
S先生:はは。Eさん得意のエネルギー分野にもありますよ。つまり、バイオエタノールとか、バイオマスとか。
E 氏:そうかっ。うっかり忘れていた。生物はエネルギーになるんでした。
Dさん:ごめんなさい。バイオマスって何なの。分からないんだけど。
S先生:ああすみません。ちゃんと説明しなければならなかったですね。バイオマスというのは、生物から作る資源のことです。たとえば、森で木を切った時の切りくずや、家畜の排泄物や、食品廃棄物などを加工して、燃料などに利用したりするものです。
Dさん:へえっ、そうなんだ。なんか生物由来だと、体にやさしい気がするわ。
S先生:そうなんですよ。バイオマスは、カーボンニュートラル、つまり燃焼しても大気中のCO2を増やさないことでも注目されています。あと、Cさんが言われていたように、AIも、ヒトの脳との関係を考える上では、ライフサイエンスの関連だと言っていいかもしれませんね。
C 氏:そうか。やっぱり。でもAIがライフサイエンスになると、あまりにも広すぎないですか。
S先生:はい。そうですね。これについては、長くなってしまうのでまた別の回に話をさてもらいます。ただ、ちょっとよもやま話としてお話ししておきたいことがあります。保健医療、農業生産、環境保全、工業生産というと、それぞれ、関係する国のお役所があります。何でしょうか。分かりますか。A君は。
A 君:えっと、農業生産は農林水産省、環境保全は環境省。えっと・・・ごめんなさい。省庁の名前をよく覚えていないです。
E 氏:保健医療は厚生労働省、工業生産は経済産業省ですな。
S先生:そうです。ライフサイエンスは、とても多くの省庁が関わっています。だからこそ、いろんな省庁が手を組んで、議員さんに動かしたりして、大きな予算を取ったり、大きなプロジェクトを起こすことができるようになってきたのです。この、広がりを持つというのが大切です。では、このようなライフサイエンスが、行政の中でどのように発展してきたか、次回以降にお話ししていきますね。今日の講義はここまでにします。
一 同:ありがとうございました。
(第1回講義 了)
公益財団法人ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔