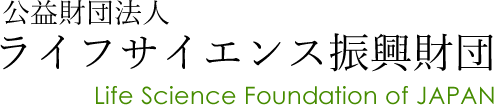第67回 火星に生命がいたかもしれない?
1.はじめに
火星の表面の探査車により、普通とは異なるタイプの岩石が発見された。それにより、火星にはかって生物がいたのではないかとの憶測が広がっている。今回はこのことについて、背景等も含めて分析・考察を行う。
2.火星の生命の可能性
(1)火星の生命への期待
火星に生命がいる、またはいた可能性は、古くから指摘されていた。19世紀中頃まで、火星は惑星の中でも地球に近く、また1日の長さが地球とほぼ同じ、さらに赤道傾斜角が地球と近く、四季がある。そして、水もあるだろうという推測がなされ、火星に生命はいるという考え方も自然に受け入れられていた。
19世紀後半になると、望遠鏡による観測で、火星の運河の存在が指摘され、知的生命の存在も指摘された。これは後になって、光の錯覚だったことが判明したのだが、火星の運河が契機となって生命の存在への期待は膨らんだ。19世紀の終わりにはH.G.ウェルズが、タコ型の火星人が地球に襲来することを描いた小説「宇宙戦争」を発表し、火星人に対する一般の人々のイメージが形成された。
(2)生命の存在への期待の萎縮
ただ、同じ頃、火星の大気の分析が始まり、米国の研究者が現在の火星の大気には水も大気も存在しないと指摘した。また望遠鏡の高度化により、運河の存在も完全に否定された。さらに生命科学の発達により、生命は非常に精緻なメカニズムを持ち、たとえ全く地球と同じ環境であっても、生命が偶然に生じる可能性が極めて低いことが分かってきた。
特に1965年にマリナー4号が火星近くを通り過ぎた時に撮った写真からは、火星は乾燥し、川も海も生命の痕跡もないことが示された。この段階で、火星に高等生物を含む多細胞生物の存在する可能性はほぼなくなり、より原始的な微生物がいるか、又はかつていたかに興味の対象は移った。そしてその後、火星には地球のように生物を宇宙線から守る磁気圏もなく、また大気圧が地球の150分の1に満たない約0.6kPaで、このため地表に液体の水が存在しないことが明らかになった。こうして次第に火星の生命への期待は萎んでいった。
(3)火星からの隕石の分析
一方、火星から到来した隕石を分析し、そのいくつかに生命の痕跡が認められたとする報告もある。隕石ができた頃は、火星の地表面は今より暖かく、かつては生命が存在していた可能性は残る。
ただ、それが本当に生命の痕跡なのか否は不確かである。たとえば、1984年に南極で見つかった火星からの隕石ALH84001について、ある研究者らは生命の徴候を発見したという主張をしたが、他の研究者らは、その観察結果は生物学的プロセスによるものではなく、地質学的プロセスによるものだとする主張をしている。
3.火星表面での生命探索ミッション
火星の生命の存在を探るため、実際に火星表面で土壌を観察したり採取したりして調べるミッションが、これまでいくつか行われてきた。
1970年代中頃に行われたバイキング計画では、火星の土壌中の微生物を検出するため、火星表面でいろいろ実験が行われた。そのうち、炭素の放射性同位元素14Cを用いた実験では、14CО2の濃度が上昇し、火星土壌中の微生物の存在が主張されたが、反対意見もあり、生命存在の確実な証拠とはされていない。
ただ近年、火星の土壌中からケイ酸塩鉱物が発見され、これは火星の表面全体で微生物による土壌生成が行われている証拠だとする報告もある。
2008年には火星の極地方を遠隔ロボットで探査するフェニックスのミッションが行われた。その目的は、火星の地層表面に微生物が生存可能な場所を見つけ、また、火星の水の地質学的な歴史を調べることだった。しかし、フェニックスから送られたデータにより、火星の土壌には過塩素塩が含まれていることが示され、それまで考えられていた以上に生物にとって厳しい環境であることが分かった。一方、地表面近くに氷の存在が確認され、また、二酸化炭素の存在も示され、生命の存在を支援するデータも出された。
4.今回の発見とその意義
2020年7月に米国NASAは、火星での活動を目的とした火星探索車「パーセベランス」を打ち上げた。パーセベランスは、翌2021年2月に火星に到着し、活動を開始した。表面の土壌を採取したり、積載していたドローンで写真を撮ったりして、そのデータを次々に地球に送ってきた。そしてその中に、古代生命の痕跡かもしれないものが含まれていたのである。
具体的には、パーセベランスが調査した古代の川床にあった岩石の表面に、中心が白っぽく縁取りの黒い、いわゆる「ヒョウ紋」模様が見られた。このような斑点は地球上でも見られるが、地球では一般に微生物の力で形成される。つまり、これは火星の微生物活動の痕跡である可能性が指摘されたのである。
その川床の岩石のあるエリアは、もし古代に微生物が存在していたとしたら、その痕跡が最もよく保存されているエリアの一つだとされていた。また、このクレーターにはかつて生命が生息できる可能性のある湖があった。この岩は、かつてこの湖に流れ込んでいた古代の川の水路で形成されたのである。そうした背景もあり、この発見は古代生命への期待感をかき立てるものとなった。
そして追加調査が行われ、その結果が2025年3月に発表された。それによると、ヒョウ紋は大きさ約1mmの小さな黒い輪で、それ以外にも、ヒョウ紋より少し小さい、黒い単一の斑点が見られ、「ケシの実」と名付けられた。
ヒョウ紋の縁とケシの実は、いずれも鉄分とリンが豊富であり、一方、ヒョウ紋中心部の白っぽい部分は鉄分と硫黄が豊富に含まれていた。このことから、岩石中の炭素を含む有機化合物が、鉄や硫酸塩鉱物と反応して化学的に濃縮され、ヒョウ紋やケシの実が形成されたことが示唆された。このような反応は、地球上ではまさに微生物によって引き起こされるものなのである。

岩石がかなり加熱されていれば、生命がなくてもこのような反応は起こりうるが、実際には岩石は粒子が細かく、つまり加熱されて再結晶化していないことが示唆される。岩石の温度が低いままだった場合、生物がその過程に関与していれば、斑点は容易に形成されると思われる。
惑星科学者によると、これは火星生命のこれまでで最も強力な証拠の一つだという。
だが今のところ、この発見は、地球外生命体の存在を主張する評価を1~7で段階的に評価するスケールで1にとどまっている。1は興味深い信号の検出、7は確実な確認をいう。つまり、確かに興味深い発見だが、まだまだ決定的ではないのである。
今回の発見は地球でではなく火星でのことであり、間接的な証拠でしかない。これをより詳細に調査するには、実験室、フィールド、モデリング等による膨大な研究を行う必要がある。そして最終的には、これを地球に持ち帰って調べる必要がある。そうすれば、現段階では1だが、今後、スケールが上がる可能性は大いにあると思われる。
5.おわりに
これまでニューズレターでは地球外生命については取り上げてこなかった。唯一「宇宙のオミックス」というテーマで紹介したことがあった(第54回 宇宙のオミックス)が、それは宇宙空間や他の天体のオミックスではなく、宇宙で活動する宇宙飛行士らのオミックスだった。
しかし、地球外生命は、生命科学のテーマとしてはかなり重要なものである。というのは、地球外生命を探索することは、生命がどのような環境で、どのように誕生し、またどのくらい過酷な環境で生存できるかを知り得る絶好の機会になるからである。精緻なメカニズムを持つ生命が容易に誕生できるとは思えないが、もしも誕生できるなら、地球の生物とは全く異なるメカニズムになる可能性もあるし、また、地球の生命自体も、隕石等で他の天体からもたらされた可能性が実証できるかもしれない。
そのような想像を巡らせるのは実に興味深く、楽しいことである。また機会があれば取り上げたい。
参考文献
・「火星の生命」(2025/01/23), ウィキペディアHP
(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E6%98%9F%E3%81%AE%E7%94%9F%E5%91%BD)
・A. Witze,“Did Mars harbor life? One of the strongest signs yet is spotted in a peculiar rock”,(2025/03/12), Nature HP
(https://www.nature.com/articles/d41586-025-00772-2)
・P. S. Anderson,“Life on Mars? Odd rings and spots tantalize scientists”, (2025/03/17), EarthSky HP
https://earthsky.org/space/life-on-mars-leopard-spots-poppy-seeds-perseverance-rover/)
ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔