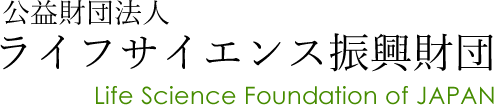第68回 新たな作用機序を持つ抗生物質の発見
1.はじめに
抗菌薬に耐性の病原体が増えてきていることから、新薬の開発が急務となっている。そんな中、カナダの研究者らは、これまで知られていなかった独特の作用機序をもつ抗生物質を発見したと発表した。今回はこのことについて、背景等も含めて分析・考察を行う。
2.抗生物質とは
抗生物質は、他の微生物や細胞に作用してその発育などを抑制する作用を持つ物質のことである。通常、放線菌等の微生物が、生存するために必要な代謝物を用いて、微生物自身が合成する。
抗生物質は、特に細菌に対して作用する抗菌薬としての用途を持ち、これまで200種類以上の抗生物質が細菌感染症の治療と予防に広く使用されてきている。また抗生物質はこの他、真菌や寄生虫、腫瘍に対して用いられることもある。
なお留意すべきことであるが、抗生物質は通常ウイルスに対しては効かない。抗生物質は、細菌のように細胞からできているものについて、その増殖や維持を行う装置に働きかけてそれを壊していくものである。このため、ウイルスのように自分自身でそのような装置を持たないものには効き目がないのである。
3.抗生物質の発見の歴史と停滞
抗生物質は、その正体や機能は知らないまま、古来より用いられてきた。カビなどが感染症の治療に使われたという記録が残されている。
しかし、抗生物質が初めて単体として分離され、機能が確認されたのは20世紀になってである。1928年、A.フレミングは、アオカビから細菌の増殖を防ぐ物質として抗生物質を分離し、ペニシリンと名付けた。H. W. フローリーとE. B. チェーンらの研究によりその大量生産が可能になると、ペニシリンは臨床試験を通じて、感染症治療薬として急速に医療に普及、絶大なる評価を勝ち得た。
この頃から研究者は抗生物質の探索・開発に取り組むようになり、初期には抗生物質を定義づけしたS. A. ワクスマンにより、結核に有用なネオマイシンやストレプトマイシンの他多数の抗生物質が発見された。
すると各研究者や企業はこぞって抗生物質の発見に努めるようになった。1940年代終わりから1970年代にかけて、エリスロマイシン、アミノ配糖体、セファロスポリン、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、マクロマイド、キノロン、トリメトプリム等、さまざまな、新たな系統の抗生物質が次々と発見されていった。
しかし、そのような新たな系統の抗生物質は、1970年代後半以降、ほとんど発見されなくなった。たとえ見つかっても、既に発見されている抗生物質と同系統で、効き目は従来のものと代わり映えしなかった。
そうなると、抗生物質の耐性菌が次第にはびこるようになってきた。それまで次々と新たな抗生物質が発見されていたがゆえ、医療機関によっては、ある抗生物質が効き目がなくなっても次のものを試せばいいやという考え方を持つようになっていたことや、患者自身もそれを抵抗なく受け入れていたことも原因だと思われる。
複数の抗生物質に対し耐性を示す多剤耐性菌の出現を受けて、世界保健機関(WHO)は抗生物質が効かなくなるポスト抗生物質時代の到来を危惧している。

4.今回の発見とその意義
(1)ラリオシジン発見に至る経緯
カナダのマクマスター大学の研究者らは、自分たちの家の庭からとってきた土壌を調べ、発見したパエニバチルスという細菌を約1年間培養した。そうして希少で成長の遅い同細菌を増やしてから、細菌を分画して抗菌化合物を探した。
この過程を通じて研究者らは、広範囲の抗生物質活性を示し、グラム陽性菌と陰性菌の両方の病原菌、及び結核を引き起こす結核菌に関連するマイコバクテリアを殺すのに効果的な抗生物質を発見した。研究者らは、これをラリオシジンと名付けた。
この抗生物質は、ラッソ形状と呼ばれる構造を持っていた。これは、単一のイソペプチド結合を含むアミノ酸のリングとして構造化された短いタンパク質である。アミノ酸の尾がその結合から伸び、リングの端を越えて中央の穴を通り抜ける。このような形状をもつペプチド、すなわち短いタンパク質のことをラッソペプチドという。

(2)ラリオシジンのメカニズム
多くのラッソペプチドはある程度の抗菌作用を示すが、ラリオシジンは細菌のリボソームに結合して細菌を殺すという点で独特である。
具体的に言うと、ラリオシジンはリボソームのアミノアシル部位(A部位)に結合する。そこは、リボソーム上でのタンパク質合成過程で転移RNA(tRNA)が結合するところになっている。ラリオシジンがこの部位に結合すると、リボソームはメッセンジャーRNA(mRNA)のコドンを正しく読み取れず、タンパク質の誤翻訳を引き起こす。これは抗菌化合物ではこれまで見られなかった作用機序である。

そこで研究者らは、スーパー耐性菌(多剤耐性細菌)として知られるアシネトバクター・ラウマニに対する効果を調べたところ、効果的に殺菌することが分かった。一方、ヒト細胞株に対しても試験を行った。すると、ヒト細胞に対しては毒性を示さないことが分かった。これは、ヒトのリボソームが細菌のリボソームと十分に異なるため、ラリオシジンが結合できないためだと思われる。
さらに研究者らは、マウスにアシネトバクター・ラウマニを感染させ、その後ラリオシジンを投与した。すると、投与したマウスは投与後48時間で全て生存していたのに対し、投与しないマウスは生存しなかった。
これらのことを踏まえると、今後、ラリオシジンが医療等の現場で多剤耐性菌への感染に対する有効な治療法になることが期待される。ただそのためには今後、様々な動物実験や臨床試験を行っていく必要があるだろう。
5.おわりに
抗生物質は人類が感染症と戦うに際し、自然の恵みとしてもたらされる最高の武器である。しかしせっかく武器を数多く所有していても、細菌がそれに対する耐性を備えるようになると、さらに強力な武器を用意しなければならなくなる。
このような耐性菌の出現は、前述のように医療機関や生活の上で安易に抗生物質が多用されたことの弊害である。疾病治療は何よりも優先されるものの、その上で、不必要な抗生物質の濫用は慎まねばならない。
ましてや意図的にかかる耐性菌を作出するような研究には厳重な規制が必要である。私がかつて担当していた遺伝子組換え技術に対する規制では、既存の薬剤が効かなくなるような耐性を持たせるよう微生物を改変するような研究は、文部科学大臣が確認する必要があるとされている。また米国のNIHガイドラインでも、この種の研究は多くの遺伝子組換え研究がある中で、唯一NIH長官の承認を必要とする研究とされている。
なお研究者らは、本研究は米国イリノイ大学の研究者らとの国境を越えた協力なしには不可能だったと述べ、合わせて、米国とカナダの間の紛争が不要な混乱を引き起こし、将来の協力を複雑にしているとしている。トランプ政権の施策がここにも影響をしている。人々を各種疾病から守るためには生命科学研究や医療研究を、国際協力を行いつつ推進していくことが不可欠なのは言うまでもない。
米国が他の国々と協調しつつ健全な政策に復帰するよう筆者としては期待したい。
参考文献
・S. Mallapaty “New antibiotic that kills drug-resistant bacteria discovered in technician’s garden”(2025/3/26) Nature HP
(https://www.nature.com/articles/d41586-025-00945-z)
・M. Barnhart, “New class of antibiotic found in soil sample”, (2025/3/28) Chemical and Engineering News HP
(https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-discovery/New-class-antibiotic-found-soil/103/web/2025/03)
・「抗生物質」(2025/4/1), ウィキペディアHP
・岡島俊英et.al.(2019)「多剤耐性細菌に有効な次世代型抗菌薬耐性細菌の出現しない抗菌薬の開発は可能か」Kagaku to Seibutsu; Vol.57(7), 416-427(図を引用)
・バイオ先生「mRNAからタンパク質へ!翻訳の仕組みを詳しく解説!」(2022/10/9)じっくり医療講座(図を引用)
(https://easy-bio-blog.com/genetics-translation-initiation/)
ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔