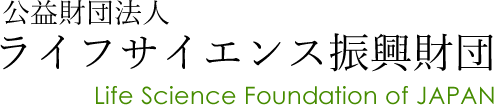第75回 中国はライフサイエンスで米国に追いつけるか
1.はじめに
科学技術の各分野で中国は目覚ましい進展を遂げている。既に科学技術分野全体としては、有名誌に掲載される論文数では米国を上回っているが、はたしてライフサイエンス関係はどうか。
ここではネイチャーインデックスやその他の統計・資料等を踏まえ、同国のライフサイエンスの現在や今後の動向について分析・考察する。
2.ネイチャーインデックスによる各分野別の比較分析
ネイチャーインデックス(Nature Index)は、研究機関のパフォーマンスを評価する指標であり、シュプリンガーネイチャー社が調査・作成している。
分野としては、化学、物理科学、環境・地球科学、生物科学(biological science)、及び健康科学(health science)の計5分野を評価・作成の対象としている。
なお健康科学は、自然科学としての生物科学に分類されない臨床医学や外科の領域が中心になっている。ここでは生物科学分野と健康科学分野をあわせてライフサイエンス関連と呼ぶことにする。
対象になる研究成果は、科学者が重視・推奨する科学誌145誌に掲載された、いわゆる一流の論文である。「シェア」と「カウント」の2つの指標で評価され、「シェア」はいわゆる分数カウント、「カウント」は整数カウントである。詳細は以前のニューズレター(第52回 生命科学の論文数から見た各国・研究機関の状況)を参照されたい。
下の表は2024年4月から2025年3月までの1年間に、Nature Indexが対象とする5分野について、主要科学誌145誌への掲載論文数を、シェア数の上位20か国で示したものである。

それによると、中国はこれら5分野をまとめた全分野のシェア数において、既に米国を抜いて世界一になっている。そして、5分野のうち、化学、物理科学、地球・環境科学の3分野において、世界一である。
一方で、ライフサイエンス関連すなわち生物科学と健康科学の2分野においては、依然として米国が1位であり、中国は2位である。この2分野のシェア数は、生物科学分野では米国8,176に対し中国4,094、健康科学分野では米国5,005に対し中国1,755と、それぞれ倍、3倍離れていることである。つまりライフサイエンス関連では、まだまだ米国の圧倒的優位が続いているのである。
3.中国が分野に比べ生命科学分野で米国に追い付いていない理由
本年6月のネイチャー誌には、中国のライフサイエンスの現状や将来について、神経学者で本年3月まで北京の首都医科大学の学長であった饒毅(饶毅、Yi Rao、詳しくはこちらを参照されたい)氏へのインタビューが掲載されている。同氏は、中国における科学・教育改革を牽引してきたことで知られる。米国でキャリアを積み、2007年の中国帰国後、終身在職権制度や、ピアレビューによる研究者の功績評価等を導入し、同国の生命科学研究を活性化させてきた重要人物だ。
同氏によると、米国がライフサイエンスで依然として優位なのは、ひとえに、米国には国立衛生研究所(NIH)があるためだとのこと。
次の表は、Nature Indexでライフサイエンス関連における世界のトップ20機関を示したものである。

この表を見ると、上位20位までの相当の部分を米国の機関が占めている(生物科学分野10機関、保健科学分野14機関)。饒毅氏が言及しているNIHは、生物科学分野で3位、健康科学分野で2位であり、決して圧倒的な1位というわけではない。むしろ、米国は一極集中ではなく、同国には論文を量産している機関が多数あるということである。
他方NIHは、研究機関としての性格とともに、世界最大のライフサイエンスの資金拠出機関としての性格も持つ。したがって、NIH自体のNature Indexシェア数は圧倒的ではないが、ここに掲げられた他の米国機関のほとんどがNIHから莫大な資金拠出を受けていると想定される。
饒毅氏が、米国が優位である原因はNIHの存在であるとしているのはこのことであり、米国と中国の差は資金の差にほぼ比例しているのである。
同氏によると、中国は、NIHに相当する機関を持たない限り、米国に後れを取ることになるとのこと。それはすなわち、資金拠出をより集中して行える仕組みを持つということだろう。
4.米国のライフサイエンスの失速
しかし、米国はトランプ政権になって、新たな事態が生じている。同政権は、本年10月から始まる2026会計年度のNIH予算は275億ドルにすることを表明している。これは前年度に比べ180億ドル、40%もの大減額である。
今後、議会でどのような議論になるか分からない。第一次トランプ政権時には、超党派やロビイング活動により結果的にはNIH予算は増加した。だが、今回は、同政権はかなり本腰を入れて減額に取り組んでいるとみられており、関係者の不安は高まっている。
また、特にハーバード大学やコロンビア大学等、イスラエルに反発する大学に対しては同政権の風当たりは強い。Nature Indexのライフサイエンス分野で1位に君臨しているハーバード大学では、今後複数年にわたり約600件、22億ドルもの助成金が中止されることになっている。そして、外国人留学生の受け入れ資格の剥奪は、異なる背景の研究者の切磋琢磨による新たな研究アイデアの創生や、留学生等の米国での活動継続による研究の達成を阻むものとなる。
今後、政権交代までこのような措置が継続するかどうか分からないが、たとえ一時的にせよ、米国のライフサイエンスへの支援が抑制されたことで、その進展が失速することになるだろう。
5.中国のライフサイエンスの今後
米国がそのような状態でもたついていると、いくら現状では離されているからといっても、中国が将来的には逆転する可能性が大いにありそうである。実は、既に現状でも、その兆候は見られている。以下、饒毅氏のコメントを中心に、事実関係等は著者が補足する。
本年4月にネイチャー誌に掲載された記事によると、中国は直近1年間のがん研究の成果においては、既に米国を上回り世界一になっている。2023年から2024年の間に米国の同分野でのシェアの増加は5%だったが、中国はなんと19%も増加しており、それが逆転につながったとのこと。
ただ、中国は、データが大量に蓄積されていると思われる精密医療においては、意外にも米国に後れを取っている。饒毅氏によると、これは中国において、ヒト自体の遺伝子研究がそれほど進展していない一方で、あまり意味のないDNAシーケンシングばかりが過剰に行われていることに原因があるとのこと。また、実は中国はこれまで、それらの大量データからデータセットをあまり整理できていない。その理由としては、各病院や、病院内の医師たちが利害を争って互いにデータセットやデータベース構築のための協力を行おうとしないためだとのことである。同国研究者らは、自国の作製によるデータベースよりもむしろ、NIH等のデータベースのデータで研究を行っているのである。しかし、皮肉にも、トランプ政権が中国によるかかるデータベースへのアクセスを禁止したことで、この状況が改善されることが予想される。つまり、これにより、中国の病院や医師らは、皆が団結してデータ共有していく必要性を認識し始めたということである。
また饒毅氏によると、遺伝子治療では、米国が躊躇していることが中国にチャンスを与えてくれるとのこと。かつて騒がれた遺伝子編集ベイビー(第3回 遺伝子編集ベビーのその後)等、行きすぎた暴走は同国内でも批判を招くが、動物実験では遺伝子組換えザルを大量に保有しており、また臨床においても希少疾患患者が多い中国は有利だろう。
なお同国の研究機関としては、北京大学、北京協和医学院、上海交通大学など主要大学の医学部、中国科学院傘下の研究機関(生物物理研究所、微生物研究所、昆明動物研究所など)、北京生命科学研究所、中国医学科学院といった研究機関が今後ますます重要な役割を果たしていくと思われ、饒毅氏は、医療分野では、中国はAIとオミックスデータバンクの力を借りて、遺伝子治療、神経変性疾患、代謝性疾患、がん等の分野が発展していくと予測している。
なお、医療分野以外では、現状でも、植物生物学において、中国は米国を上回ってきている。饒毅氏としては、植物生物学の優位は資金の規模によるもので、中国は食糧安全保障を懸念し、同分野に米国よりはるかに多額の資金を投入してきている。そして将来的にも、農業分野全般で同国は優位に立ち、新たな種子の登場等により同国のバイオテクノロジーは飛躍的に発展すると予測している。
6.日本について
今回の分析テーマは中国と米国の関係だったため、日本に関してはあまり触れてこなかったが、簡単に言及しておく。
日本はライフサイエンス関係では生物科学で世界第5位(シェア685)、健康科学で世界第10位(シェア269)である。だが、先述の米国・中国のシェア数と比べると、順位以上に両国とは大きな差がある。一方、カウント数においては、生物科学では7位、健康科学では13位と、シェア数に比べ順位を下げている。シェア数に比較してカウント数で劣位にあるのは、日本では内向きの研究にとどまり、国内の他機関や国外機関との共同研究や研究協力が進んでいないことが原因と思われる。
また、ランクインしている研究機関数も少ない。100位までのうち、生物科学分野では東京大学(24位)、京都大学(60位)、大阪大学(100位)のみであり、健康科学分野にいたっては100位以内に1機関も含まれていない。
日本は、米国のようなライフサイエンス大国を目指し、2015年、同国のNIHを参考に日本医療研究開発機構(AMED)を設立した。もう設立後10年になるが、これはいったいどうしたことだろうか。今後、真剣にその原因を調べて対応を検討していかねばならないだろう。
7.おわりに
Nature Indexを用いた中国の進展状況や今後の予測を見てきた。
以前から言われているのは、中国は確かに論文数は多いが、質の劣るものばかりで真に優れた研究はない。このためノーベル賞受賞者はいない、という論法である。
ただ、著者の考えでは、こうした著名雑誌への掲載が多くなってきた現状では、それはありえないと思われる。 確かに優れた雑誌にも、ノーベル賞級の超独創的な研究とそうでない研究があるが、中国研究者の論文だけはそのような超独創的な研究からことごとく外れているというのは穿った見方だろう。
特に、米国で活躍している中国出身のノーベル賞受賞者や候補者は多いが、そうした人々が米国の対中国政策によって中国に戻されたり、又は中国の海亀政策等によって中国に帰国するなら、同国のライフサイエンスはいっそう進展すると思われる。
さらに、同国のカウント数を考えると、米国なしでも他国との共同研究や研究協力により発展していくものと、逆に米国は中国との協力なしではライフサイエンス分野の成長は損なわれると思う。
今後の動向は実に興味深い。
参考文献
・J. Dreyer (2025), “How China can become a biotechnology superpower”, Nature; Vol.642, 50-571
・J. Dreyer (2025), “Here’s why China’s science and innovation model is thriving”, Nature; Vol.642, s6-s7
・“China overtakes the United States in cancer research output” (2025/4/23) Nature Index(https://www.nature.com/articles/d41586-025-01154-4)
・Nature Index (https://www.nature.com/nature-index/)
・中国の科学技術HP 首都医科大学 https://china-science.com/cmu-peking/
ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔
編集者・林のコメント
当記事を掲載するニュースレターの発行者であり編集者である林(ライフサイエンス振興財団理事長)は、長年中国の科学技術の動向を調査分析してきた。そこで、上記の記事について簡単にコメントしたい。
1.Nature Indexは指標の一つ
科学技術の国際的な競争力を見る場合、Nature Indexも一つの指標であるが、これだけで断定すべきではない。林は、科学論文数、Nature Index、日本の専門家による関係分野の評価、著名国際賞と引用栄誉賞での評価の4つを国際競争力の分析に用いており、これらによると、中国のライフサイエンスを含む国際競争力は、論文やNature Indexでは米国を含めて世界を圧倒しているが、専門家の評価や著名国際賞受賞者では米国や欧州よりはるかに劣り、日本とほぼ同等となっている。
〇SCI論文数:クラリベートアナリティックス社の論文データベース(SCI)を用いた論文数比較で、中国は全分野で世界一であり、引用数を考慮した質の高い質の論文・Top1%論文数でも米国を抜いて世界一となっている。詳しくはこちらを参照されたい。
〇Nature Index:上記佐藤氏の記事のとおりである。
〇日本の専門家による関係分野の評価:JST・CRDSによる「研究開発の俯瞰報告書(2023年)」をもとに、林が分析した主要国地域の科学技術力国際比較は次のとおりであり、現状では中国は米国や欧州と距離があるとの評価となっている。詳しくはこちらを、また、その分析手法はこちらをそれぞれ参照されたい。
○環境・エネルギー分野 欧州~米国>中国~日本>韓国
○システム・情報科学技術分野 米国>欧州~中国~日本>韓国
○ナノテクノロジー・材料分野 米国>欧州>日本~中国>韓国
○ライフサイエンス・臨床医学分野 米国>欧州>日本~中国>韓国
(註)「~」は左の国・地域が右の国・地域と同等であるか若干強いと言うことであり、「>」は左の国・地域が右の国・地域と顕著な差があると言うことである。
ライフサイエンスについて、経年変化を示したのが下図である。詳しくはこちらを参照されたい。

〇ノーベル賞受賞候補での日中比較:ノーベル科学三賞は著名な国際賞(ライフサイエンスではガードナー賞、ラスカー賞、ウルフ賞など)の受賞者やクラリベート社が毎年発表している引用栄誉賞受賞者の中から選ばれることが多く、これらの著名国際賞などを受賞した日中の研究者数を比較すると、日本が中国を圧倒している。詳しくはこちらを参照されたい。なお、米国や欧州の科学者について評価・分析していないが、著名な国際賞はほとんど欧米主導であり、受賞者数で日中を凌駕していることは間違いないと考えられる。
2.これらの指標での結果の分析
前の二つの指標と後の二つの指標では、中国の評価が大きく違っている。前者の数量的なものを機械的に評価する指標では中国が世界を圧倒しているが、後者の関係分野における専門家の評価(ピアレビューと呼ばれ、ノーベル賞の選考もこれに該当する)では、米国や欧州、さらには日本にも劣るという結果となっている。中国は、膨大な研究者数と旺盛な論文作成意欲に支えられて論文数などで世界を圧倒しているが、中国の研究者は欧米の研究者に比してオリジナリティのある独創的なものが多くないため国際的なピアレビュー評価で劣っているというのが、現在の林の結論である。
3.今後の予測
将来的に、異なる指標での乖離が変化するかどうかであるが、中国の研究者がオリジナリティを徐々に発揮していくとすれば、ピアレビューを用いた指標でも欧米に追い付き、追い越すことも可能であろう。
また、米国のトランプ政権の科学技術政策は、米国の科学技術力を劣化させる自傷行為であり、これを続けていけば佐藤氏の言うように、中国を大きく利することになるであろう。ただ、私はトランプ政権のこのような政策は一過性のものであり長続きしないと、希望的に考えている。
ライフサイエンス振興財団理事長・国際科学技術アナリスト 林幸秀