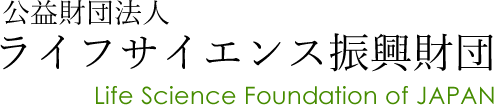第76回 機能獲得研究に関する米国の動向
1.はじめに
米国トランプ政権では、機能獲得研究(GOF研究)について、全面的に中止する動きがみられている。ここでは最近の動向と今後の展望について分析・考察したい。
2.機能獲得研究とは
「機能獲得(GOF:gain of function)」とは、一般に生物に新たな性質を付与することを言うが、特に、ウイルス等の微生物に各種の変異を与えることで、感染性、病原性、生存能力などを増大させる研究を「機能獲得研究(GOF研究)」と呼ぶことが多い。
3.第二次トランプ政権前までの動き
GOF研究の動向については、何度かこのニューズレターでも紹介している(第19回「機能獲得研究」に対する米国の検討状況について等)が、まず第二次トランプ政権前の状況について、簡単に整理しておく。
GOF研究がはじめて本格的に議論されたのは、2012年に、河岡義裕・東京大学名誉教授(当時米国ウィスコンシン大学教授を兼任)のグループ及びR. フーシェ博士(当時オランダのエラスムス医療センター)のグループが、別々に行った研究結果を発表した時だった。彼らはそれぞれ、H5N1鳥インフルエンザウイルスを改変して、哺乳類であるフェレットに感染させるようにさせたのだが、その研究結果の取扱いが物議を醸した。
これらの研究が注目を浴びたことから、世界保健機構(WHO)での検討を通じ、国際的にモラトリアムすなわち研究自粛の呼びかけがなされた。米国では2014年に、国立衛生研究所(NIH)がWHOでの呼びかけを踏まえGOF研究とみなされる18のプロジェクトに対する資金拠出を全面的に中止した。ただしその後、研究者らからの要請も踏まえ、一部は再開が容認された。
米国ではその間、GOF研究のコスト・ベネフィットについての検討が行われ、NIHを所管する連邦政府保健福祉省(HHS)が2016年に、その諮問機関である「バイオセキュリティのための国家科学諮問機関(NSABB)」の報告も踏まえ、NIHに提出された研究のうち、特定のGOF研究、すなわちパンデミックを引き起こす可能性のある15の病原体を用いた感染力の増大研究や、根絶された病原体の再現研究等については個別に追加審査を行うこととし、2017年にはそのためのガイドラインを公表した。
しかし、実際には同ガイドラインに沿った追加審査の網にかかるGOF研究は極めて少なかった。このためNSABBは再度検討を行い、審査の網を広げる方向で報告書案をまとめようとした。ただし確認できてはいないが、同報告書は最終的にオーソライズはなされておらず、結果としてGOFとみなされるような研究のうちのかなりの案件はそれまでのガイドラインに則り審査の対象外として助成金が与えられていたと思われる。
4.コロナウイルスを巡る議論とトランプ政権の考え
そのような経緯の中、本年1月、第二次トランプ政権が発足した。そして同政権は本年4月、新型コロナ感染症(COVID-19)の原因ウイルス(SARS-CoV-2)について、中国での研究の過程で流出したとの見解を公表したのである。
その根拠としては、まずSARS-CoV-2がそれまで自然界に見られなかった独自の生物学的性質を有していること、またCOVID-19の初期発生地である中国の湖北省武漢市にはSARS-CoV-2と構造の類似した重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因ウイルス(SARS-CoV)等を扱う中国科学院武漢ウイルス研究所があり、同研究所ではバイオセーフティが不十分な状態でGOF研究を実施されていたとするものである。
つまり、それまでSARS-CoV-2の発生源についての考えとして主流を占めていた、武漢市の食肉市場においてセンザンコウ等の動物からヒトへ感染したという野生動物感染説を真っ向から否定し、武漢ウィルス研究所でのGOF研究がその原因だと断定したのである。
武漢ウィルス研究所からのウイルス漏洩説は、以前からあった。そもそもトランプ大統領自身を含む一部の科学者や共和党議員が、コロナのパンデミックのさなか、原因となったウイルスはNIHの資金提供を受けていた武漢ウィルス研究所で行われたGOF研究から生じたと主張した。
そして、それを科学的に裏付けるべく、2020年には米国のローレンス・リバモア研究所が、SARS-CoV-2のゲノム解析からCGG-CGGという、ウイルスの感染力を高めるために人為的に挿入される配列を発見したという報告を行った。また2021年には英国の科学者が、SARS-CoV-2の感染性にとって重要なスパイクタンパク質の部分に正電荷のアミノ酸が4つ並ぶという、自然の変異ではなかなか得られない構造を発見し、それがヒトへの感染性を高めたという報告を行った。
それらだけでは、ウイルス漏洩説の決定的な証拠とは言い難い。だが、そこに政治的要素が加わったことで、話が複雑化した。
バイデン政権当時に国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)の所長で新型コロナ対応の指揮を執っていたA.ファウチ氏は、武漢ウィルス研究所漏洩説に関する報告は重視せず、ウイルスの動物からの感染説を提唱した。これには非営利団体エコヘルス・アライアンスのP.ダスザック氏らが大いに賛意を示した。ダスザック氏は、WHOによる武漢での現地調査に米国唯一のメンバーとして参加し、武漢ウィルス研究所漏洩説を否定するWHO報告書の作成に貢献した。
だが、ダスザック氏は武漢ウイルス研究所の研究者らとの論文を十数本も共同執筆しており、また同氏が所属するエコヘルス・アライアンスはNIH等から受け取った連邦助成金のうち60万ドルもの資金を武漢ウイルス研究所に提供しており、中国との結びつきが強かった。さらに、同研究については、先述のHHSでの追加審査の対象にはなっていなかったのである。
こうしたことから、WHO報告書が出されたにもかかわらず、真実がいずれであるのか判断がつきにくい状態だった。ただ先述のように、当初から一貫してトランプ大統領は、武漢ウィルス研究所漏洩説を支持・主張していたのである。
5.GOF研究への助成停止
(1)大統領令の発令
そして本年5月5日、トランプ大統領は、いわゆる危険なGOF研究への助成金を停止する大統領令に署名した。この停止は大統領令の発令後4か月間、つまり9月初めまで行われることになった。そして、その間に政府は、GOF研究を資金提供機関や研究機関がどのように監督するかについて、新方針を打ち出すとこととされた。
同大統領令では、危険なGOF研究として、感染性病原体又は毒素に関する研究で、それらの致死性又は伝染性を高める可能性を持つものとしている。これには、病原体に対し、ワクチン・治療薬・検出を回避する能力を与える研究等も含まれている。
同大統領令は、中国、イランその他の懸念国で行われる、危険なGOF研究に対する連邦政府資金の提供も禁止した。また、適切な監督体制が整っていない国については、公衆衛生に脅威となる可能性のある生命科学研究への資金提供を停止することとした。そして、生命科学分野にける連邦政府助成金の受領者は全て、関連研究において外国と共同研究を行っていないことの確認等を行い、大統領令を遵守する必要があるとした。
なお本大統領令に反した研究機関は、最長5年間、連邦政府からの資金提供を禁じられることも示唆された。
(2)NIHの措置
現在、上記の大統領令を踏まえ、NIHにおいて具体的な措置が行われつつあるところである。
詳細は公表されていないが、まずNIHは危険なGOF研究の定義に該当する可能性のある研究として、当面40件のプロジェクトを特定し、リスト化した。その中には、一般にもよく知られているCOVID-19、インフルエンザ、デング熱、ジカ熱を引き起こすウイルスの研究や、あまり知られていないアルファウイルス、ブニヤウイルス、フレボウイルス等の研究も含まれている。
また、NIHから各研究者に対し、順次、研究停止の通知が出されつつある。リスト中の9件はNIH自身の所内研究者によって実施されているが、彼らは既に研究を中止又は変更することに合意しているとのこと。
さらに、このリスト化された40件以外に、172件のプロジェクトが一時停止又は終了の可能性があるとのことである。
これら、連邦政府の行う研究停止要請は、あくまで資金拠出の停止であり、安全面での研究禁止ではない。なので理論的には、自己資金で研究を行っていくことは可能である。しかし、米国の研究機関の大部分が連邦政府資金に大きく依存している以上、自己資金で研究を行いその成果が公表された場合、当該機関への連邦政府資金の拠出や医薬品等への実用化に際しての審査への影響が出てくる可能性は大いにあり、自己資金によって研究を継続していくことは難しいと思われる。

NIHが中止した研究の多くに用いられている
6.米国研究者らの反響
こうした連邦政府の一連の措置は、同国の研究者らに大きな不安と混乱を引き起こしている。特に、これまでNIHは、今回の決定について詳細な説明を一切行っていないことが、研究者らの不安を高める一因になっている。危険なGOF研究や停止されるGOF研究について、具体的な選定理由が分からないのである。
リストの中には、そもそも危険なGOF研究の定義にそぐわないと考えられるものも存在する。
たとえばリスト中には2種類の致死性ウイルスに対する防御抗体を調べる研究があるが、この研究ではそもそも実際の病原体は扱っておらず、なぜリストに含まれたのか疑問が生じている。
また、停止された研究の中には、結核を引き起こすマイコバクテリアに機能喪失を起こさせるような研究も含め、結核菌についての研究が多く含まれている。だが、結核菌は既に人類の4分の1が潜在的に感染しているが、強い有害性を持つようになったことはほとんどない。
さらに、たとえ結核になっても大部分は治癒可能である。このため研究停止までする必要があったか疑問を持つ研究者もいる。
加えて、インフルエンザウイルスをがん治療用に改変する研究等、有用性が高いと考えられる研究も停止されている。
こうしたことを過剰に受け止め、研究者が、公衆にそれほど高いリスクをもたらさない研究であっても、自ら判断してやめてしまうのではないかとの懸念がある。また、研究者は、研究時にウイルス等に導入する変異により、ヒトに対してより病原性や伝染性を持つようになるかどうかを予測できないことが多い。このため、今後はそうした研究を完全に避けなければならないと考えている研究者も多い。
ただし一部ではあるが、リスクのある研究に関する規制がさらに厳しくなる可能性のあるこの大統領令を歓迎する研究者もいる。
7.おわりに
米国では、これまでGOF研究を巡っては、さまざまな議論を積み重ね、確認しつつ進めてきた経緯がある。しかし、トランプ政権ではそのような経緯をほぼ無視し、完全停止を図った。そのようなやり方はあまり効率的ではなく適切ではないと思われるが、他方でGOF研究が安全側に大きく振れたことには間違いない。
今後、停止された研究がどのように扱われていくのかフォローしていきたい。
なお、日本ではGOF研究に特化した規制はなく、生態系影響の防止等を図るために制定されたカルタヘナ国内法の下で、遺伝子組換え技術に対する規制が行われている。同法は本年3月、省令等の改正が行われたが、ウイルスや細菌等に病原性等を高めるような改変を行う場合は各機関での承認に加え、文部科学大臣の確認が必要とされている。つまり、GOF研究については実質的には同法である程度は担保されていると考えられる。
だが同法は、生態系影響や安全(セーフティ)面での対策が中心で、危険なGOF研究を強制的に禁止したり、その成果の公表を制限したりする等、セキュリティ面を中心とした具体的な措置は定められていない。
米国の動向を踏まえた日本でのGOF研究に対する規制が今後どうなるか、関心を持ちつつ見守っていきたい。
参考文献
・J. Cohen et. al. (2025), “NIH suspends alleged ‘gain-of-function’ studies”, Science; Vol.389, 223-224
・S. Mallapathy, “Trump freezes ‘gain of function’ pathogen research ― threatening all US virology, critics say”, (2025/5/7), Nature HP
(https://www.nature.com/articles/d41586-025-01411-6)
・楊井人文「ウイルスを増強する機能獲得研究「国内で把握する仕組みも規制もない」米国は監視体制強化へ」(2025/5/18), YahooニュースHP
(https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/cba7851e3194b1ed0327fce8da6009a08514da98)
・藤和彦「武漢ウイルス研究所流出説、海外で再び広がる…ファウチ所長のメール公開、風向き変わる」独立行政法人経済産業研究所HP
(https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/fuji-kazuhiko/274.html)
ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔