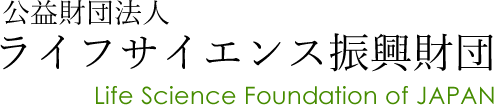第77回 ヒ素生命の論文が撤回される
1.はじめに
2010年にサイエンス誌で公表され、科学界に大きな衝撃を与えたヒ素生命の存在に関する論文が、公表から15年も経った本年7月、同誌から正式に撤回された。今回はそれについて、背景・経緯とともに分析・考察する。
2.ヒ素生命の論文についての経緯
(1)衝撃的な発表
2010年12月、米国航空宇宙局(NASA)が突然、地球外生命体に関する会見を開くと発表した。発表の主体がNASAだっただけに、さては宇宙人が発見されたのかと世の中は騒然となった。
その後、NASA宇宙生物学研究所の研究者等からなるチームが記者会見を行った。発表された内容は、地球外の生命が発見されたというのではなく地球上の生命に関するものだったが、それでも衝撃的なものだった。彼らは猛毒のヒ素(As)を豊富に含む微生物を米国カリフォルニア州のモノ・レイクという湖で見つけたが、その微生物は、地球の生命の共通ルールとは異なるルールに従っている可能性があるというものだった。

生命の共通ルールとは、生物の遺伝情報は親から子に伝えられ、DNAは炭素(C)、水素(H)、酸素(O)、窒素(N)、リン(P)でできているというものである。微生物から植物、動物に至るまで、この共通ルールから外れた生物はいまだ見つかっていない。
NASAの研究チームは、モノ・レイクにあるヒ素(As)の濃度の高い泥から微生物を採取した。そしてそれを、リンの代わりにヒ素を含む培地で育てたところ、DNAにヒ素が取り込まれていることが分かり、彼らはこの微生物を「GFAJ-1」と名付けた。
リンとヒ素は元素周期表で上下に位置する同属元素であり(リンは第3周期、ヒ素は第4周期)、化学的性質が似ている。このため、リンではなくヒ素を取り込むことで生存する生物が独自に進化している可能性もあると考えられた。
そうした内容は、サイエンス誌にオンラインで掲載された。

(受験のミカタHPより佐藤が加工)
(2)同論文に対する批判
しかし、この論文が掲載された後、科学界では同論文に対し大きな批判が巻き起こった。化学者たちは、もしDNAの骨格にヒ素が組み込まれれば、結合は非常に不安定になり、水中で1秒も経たないうちに分解してしまうだろうと主張した。また微生物学者たちは、細菌の培養培地に十分な量のリン酸が混入していたこと等、研究の欠陥を指摘した。
さらに、同論文では、GFAJ-1がヒ素を取り込んでいることは示されているが、ヒ素を含む有機化合物は全く確認されていないことも問題視された。選択的質量分析法という方法を用いれば、DNAやRNAにヒ素が含まれていることを直接確認できたはずだと指摘された。
今回のデータそのものが、周囲にある微量のリン酸塩を利用しながら、ただヒ素酸塩を吸収して分解する生物なのではないかと考える研究者もいた。この生物は膨らんでいるように見え、大きな液胞のような構造体を含んでいる。液胞は毒物を隔離する目印であることが多い。さらに、ヒ素酸塩で増殖するこの細菌は細胞周期の静止期に分析されているが、正式には活発な増殖時ほど生存のためのリン酸塩が必要ではないとのこと。

このため、論文のオンラインによる公開の後、サイエンス誌への誌面掲載は遅れ、2011年5月になってやっと掲載された。だがその際、同誌は論文の結論に異議を唱え、上記のような論点も含め、8つのテクニカルコメントを論文につけて掲載した。
そして2012年になると、米国とスイスの2つの研究チームは、同報告は間違いであるとの論文をサイエンス誌に発表した。それらは、NASAの研究チームと同じ細菌試料を用いて結果を再現しようと試みた。だが、同細菌はヒ素が多くてリンが少ししかない環境でも育つことはできたが、リンが全くない環境ではリンの代わりにヒ素を使って生きることはできなかった。そのことから、GFAJ-1の成長には他の既知の生命体と同様にリン酸が必要であり、この微生物はヒ素に耐えられるものの、DNAの骨格形成に必要な有意なレベルでヒ素を取り込んでいないということを示したのである。
3.論文の撤回と著者らの反応
(1)論文の撤回
ヒ素生命の論文については、その発表から15年を経た本年7月24日、サイエンス誌により突然撤回された。
サイエンス誌の撤回声明によると、同論文の発表当時には撤回となる基準は主に不正行為の場合(捏造、改ざん等)に限られており、現時点においても同論文には著者側に意図的な詐欺や不正行為はないのことである。しかし、その後サイエンス誌は論文撤回基準を変更し、今回の論文のように論文で示された実験がその主要な結論を裏付けていないと編集者が判断した場合にも、撤回するのが適切だということになつたとのことだった。
(2)著者らの反応
これに対し、同論文の著者らの大部分は、その撤回を支持しない旨の電子レターに署名し、NASAとして正式に抗議する声明を出した。その理由は、サイエンス誌の論文撤回基準に関する同論文著者らから見ての不当な変更だった。
論文の撤回については、学術出版におけるベスト・プラクティスを推奨する英国の諮問機関である出版倫理委員会(COPE)のガイドラインが、一般的に使われてきている。同ガイドラインでは、「研究結果の重大な誤り」または「不正行為」によって信頼できないという証拠がある場合、編集者は論文の撤回を検討できる旨定められている。
ただ実際には、研究結果の重大な誤りによって撤回されることはなく、ほとんどの場合不正行為のせいで撤回されてきた。しかし、サイエンス誌はこの機会に、論文の信頼性が低い場合にも撤回の対象とすることにしたとのことだった。
NASAのチームの研究者らは、この論文を狙い撃ちするかのような撤回基準の変更に反発した。これまで同誌で採択された論文の中には、誤りであることが追試で証明されたものも数多く存在する。それらの論文をはたして全部撤回するのかという問題提起を行ったのである。これに対し、サイエンス誌は反応してはいない。
4.おわりに
著者として、今回の論文の動向には、発表当時から少なからず関心があった。というのは、論文の成果が本物であったならば、本当に、地球の生命の歴史を覆すような大発見になると思われたからである。それゆえに、科学界及び科学界以外からも関心を集め、何人もの科学者がその再現・検証に躍起になって取り組んだ。
その状況は、例のSTAP細胞の経緯とも似ている。いずれも世界的な発見だと騒がれ、マスメディアでも大きく取り上げられた。そしてその後、検証実験等から論文が間違いであったことが次第に明らかになってきたものの、著者自身は決してそれを認めようとしなかった。
もっとも、STAP細胞の場合は、著者がSTAP細胞作りそのもので不正行為を行った可能性もあり、それが論文撤回の原因ともなった。これに対し、NASAの論文は、多くの研究者が実験に関与しており、不正行為の可能性は低く、むしろ実験方法の不備や検証不足である可能性が高い。
前述のように、不正行為はともかく、研究結果の再現性が疑われている論文は数多く存在する。AIやシミュレーションの助けも借りつつ、簡便なやり方で検証する方法が開発されることを期待する。
参考文献
・C. Offord (2025) “Fifteen years later, Science retracts ‘arsenic life’ paper despite study authors’ protests”, Science; Vol.389, 328-329
・L. Wolf (2025) “Controversial ‘arsenic life’ paper retracted after 15 years — but authors fight back”, Nature; Vol.643, 1163-1164
・篠澤裕介「超生命体を追え! 幻に終わったヒ素細菌」(2013/1/21)リバネス(Leave a Nest)HP(https://lne.st/2013/01/21/arsenic/)
・「高ヒ素存在下で生きる生物」(2011/12/03)Nature ダイジェスト Vol. 8 No. 2
・「DNAの構造を徹底解説!~塩基の種類から発見の歴史まで~」(2022/12/26)受験のミカタ(https://juken-mikata.net/how-to/biology/dna.html)
ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔