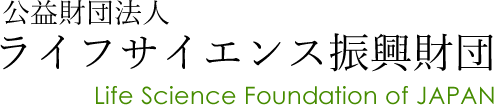第78回 米国における動物実験の代替化政策の動向について
1.はじめに
最近、米国食品医薬品局(FDA)と環境保護庁(EPA)は、特定の医薬品候補や農薬等の化学物質について、動物実験の義務付けを撤廃し、代替化を推進していく方針を示している。今回はそれを巡る背景やその影響等について、本年8月にサイエンス誌HPに掲載された記事等を踏まえ、分析・考察することにする。
2.動物実験について
(1)動物実験の目的・必要性
現在、さまざまな動物が研究に使われている。ショウジョウバエ、魚類、カエル、鳥類からマウス、ラット、イヌ、ネコ、サル等の哺乳類に至るまで、数多くの動物が使用されている。実際にはマウスとラットが90%以上を占め、イヌ、ネコ、サルは全体の1%以内だとされている。またチンパンジー等の類人猿については、大部分の国々で侵襲的すなわち体を傷つけて行う動物実験は禁止されている。だが基本的には、それぞれの研究目的に応じた実験動物が使用されている。
こうした実験動物は何のために必要か? いろいろな実験がある。動物そのものの体の仕組みや機能を知るために行う場合もあるし、ヒトの体や機能を知るために、類似したメカニズムを持つと考えられる動物で行われる場合もある。
特に多くの動物が用いられているのは、医薬の試験である。医薬候補が安全で効き目があるか調べるためには、市場化前にヒトで臨床試験(第Ⅰ相~第Ⅲ相)を行う必要がある。だがいきなりヒトで行うのは危険が伴う。このため前臨床試験として、ヒトとメカニズムが類似している動物で試験するのである。
また、化学物質等を製造・販売する場合、それが生活の場や環境中で健康影響や生態系影響等、害を及ぼすことも考えられ、その可能性のある化学物質についても動物実験を行う必要がある。
(2)動物実験の適切な施行と代替法の開発
上記のように、動物実験の種類や数は多いが、侵襲的な実験は、実験動物の痛みを伴う。このため動物実験を適切に行うため、Reduction(実験動物数の削減)、Refinement(実験動物に対する苦痛軽減)、Replacement(実験動物を用いない代替法への置換)の3Rが、国際原則として定められている。
3Rのうち、Replacementについては、単に動物愛護や動物福祉の観点からだけではなく、別の意義もある。動物実験には限界があり、前臨床試験で安全と判断された薬剤の約90%が、予期せぬ副作用のためヒト臨床実験で失敗に終わっている。その原因は、動物とヒトの生理機能の違いによるものと考えられる。このため、動物ではなく、ヒトをより模倣できるものを使用すれば効果的である。このため代替法として、これまではヒト培養細胞等が用いられてきた。ただ、それでは動物実験を完全に代替するまでには至らなかった。
しかし近年、より効果的な代替法が出現してきた。臓器チップ、オルガノイド、AIシステム等であり、これらを組み合わせて薬剤の安全性や効果を評価する方法は新アプローチ手法(NAMs:New Approach Methodologies)と呼ばれる。
個々の要素について簡単に述べると、次のとおりである。
・臓器チップ:微細加工技術を用いて、肺、心臓、腸などの生物製臓器のミニチュアモデルをチップサイズのデバイス上に作成したもの。
・オルガノイド:iPS細胞等の幹細胞を培養して作製された、臓器の構造や機能を模倣したミニ臓器。
・AIシステム:AIに膨大な事例を基に機械学習アルゴリズムを構築させることで、医薬品や化学物質の分子構造に基づいてヒトへの効果や影響をシミュレーション・予測するシステム。
なおNAMsのうち、ヒトの細胞や臓器チップを用いて生体内環境を再現したものを特に生体模倣システム(MPS:Micro Physiological System)と呼び、薬剤評価の有力なツールになっている。

(サイエンス誌HPより)
3.米国における動物実験の代替化政策の経緯
(1)米国における動物実験の所管状況
米国においては、食品や医薬品の生体影響や効果については食品医薬品局(FDA)が、また化学物質の健康・環境影響については環境保護庁(EPA)が所管している。そして、市場化に際し、必要なものについて動物実験が義務付けられている。
なお、これらとは別に、動物実験の規制自体は動物福祉法(AWA)に基づき農務省(USDA)が行っている。本法に基づき動物実験を行う全ての研究機関に動物実験委員会の設置が義務付けられ、動物の管理と取扱いが規制されている。
(2)薬剤等の市場化に際しての動物実験の義務付け
米国においては1938年、不十分な試験で薬が使用され、100人以上が死亡した事件が起きた。このためFDAはそれ以来、全ての医薬候補に対し、臨床試験に入る前に動物実験(通常は2種類の異なる動物種)を行うことを義務付けてきた。
また、EPAも歴史的に、殺虫剤や化学物質が規制に値するほど有害かどうかを判断する際には動物実験に頼ってきた。
こうした動物実験は一定の信頼性を持つと考えられたことから、FDAは緊急事態(天然痘や炭疽菌のワクチン等)においては、ヒトでの臨床試験が間に合わず、動物実験データのみを踏まえて医薬品の承認を行うこともあった。
ただ前述のように動物実験に全幅の信頼性を寄せることはできず、米国政府は、特定の薬剤等について動物実験を補完するため、細胞ベースのアッセイ、in vitro試験、ヒト皮膚モデル等、数十種類のリストを定めてきた。ただそれはあくまで動物実験の補完や追加という位置づけであり、代替とまではいかなかった。
(3)第一次トランプ政権以降の動物実験の代替化政策の変遷
こうした、薬剤評価における動物実験の事前実施を絶対とする考え方について変化が見られたのは、ここ5年くらいの間である。
まず第一次トランプ政権時の2020年に、EPAは今年すなわち2025年までに哺乳類での実験を30%削減し、2035年までに完全に廃止する旨発表した。ただ、バイデン政権時には、この計画はあまりに拙速であるとして取りやめとなった。
一方バイデン政権時の2022年、超党派が提出した「FDA近代化法2.0」が成立した。同法案は、FDAが全ての医薬品に動物実験を義務付ける要件を撤廃するものだった。
4.現トランプ政権での動物実験の代替化政策とそれへの反響
(1)FDA、EPAの状況
FDAは本年4月、先述「FDA近代化法2.0」を踏まえ、動物実験を順次廃止するためのロードマップを策定した。まずは抗体医薬品分野の開発候補を対象とし、徐々に低分子医薬や各種生物学的製剤に拡大していく方針だった。FDAはヒトへの毒性が予測可能となるよう、NAMsを数年で実現させ、動物実験を廃止できるような方向での、非臨床試験のガイドライン改定を予定している。
一方、同月、EPAのL.ゼルディン長官は前述のように、バイデン政権が覆した動物実験の段階的廃止計画を復活させる必要がある旨発表した。EPAは既に、化合物の毒性を判断する際に、ヒトの酵素が化学物質とどのように相互作用するかを測定するアッセイ等、特定のin vitro試験の使用を認めている。それに加え、EPAは、皮膚刺激性、毒性吸入、その他の指標について実施してきている動物試験を、ヒト細胞から再構成された皮膚サンプルやヒト疫学データに基づく統計予測等のNAMsに置き換える作業を進めている。
(2)NIHの状況

動物実験を含む研究に助成金を与える立場である米国衛生研究所(NIH)も、こうした動きに追随している。
NIHは本年7月、機関全体の助成金申請においてNAMsを重視すること、動物モデルのみで行われる研究に関する提案は今後募集しないこと等を発表した。
またNIHはそれに先立ち、基礎研究を治療につなげるため、非動物実験への資金提供と研修、その価値に対する認識の拡大を目的として、「研究イノベーション・検証・応用局」(OOR)を設立することを発表した。OORは助成金の査読を行う委員会と協力して、審査員の動物バイアス、すなわち従来のモデル生物を用いた研究を好む傾向を是正していくとのことである。
(3)動物実験代替化政策への反響
上述のように、現トランプ政権になって、こうした動物実験の代替化の動きが加速した。ただ、同政権は、ヒトES細胞の利用等については、ヒトの尊厳の立場から厳しい姿勢で臨んできたが、実験動物に関しては特に強い思い入れがあるわけではないと思われる。国民の間でも動物福祉の考え方は広まりつつあり、同政権がそれを汲み取ったという見方もできる。
ただ、それだけが理由ではない。FDAは、NAMsによって医薬品の評価が迅速に行えるようになり、ひいては研究コストの削減につながるとしており、それは規制緩和等で財政削減を行いたい同政権の趣旨には沿ったものになると思われる。
同政権は、ワクチン接種政策や気候変動など多くの分野で科学的コンセンサスを無視してきたが、科学界では上記の理由からNAMsへの移行はよい考えだとする声も多い。ただし、あくまでその技術が動物実験に完全にとって代わるものではなく、補完するものであればという条件付きである。
一方、特定の種を研究してきた研究者は、その研究手法をすぐ転換する可能性は低い。また、検証されていない技術への時期尚早な移行によって臨床試験が失敗した場合、NAMsの推進全体を後退させてしまうのではないかという懸念もある。
トランプ政権下では生物医学研究がかつてないほどの脅威にさらされており、新しい手法の開発と検証のための資金は、決して保証されているわけではない。
5.おわりに
米国では、このように動物実験の代替化政策が行われてきているが、一方、日本の規制においてそのような検討が行われているという話はあまり聞かない。医薬品審査においては動物実験は必須との方針は変わっていないと思われる。また、著者は今から30年以上前、化学物質を規制する化学物質審査規制法を担当したことがあるが、当時から有害だと予想される化学物質については動物実験が義務付けられ、その方針は変わっていないと思われる。
やはり、ヒトに直接適用されたり有害な可能性があったりするものについては、動物の命とヒトの命を比較考慮した場合、まだまだ動物実験は欠かせないものだと言わざるをえない。
ただ、日本でも、既に1989年に日本動物実験代替法学会も創設されており、代替法の研究は進んできていると思われる。AIも利用しつつ、動物実験を、いやヒト臨床試験までも完全にシミュレートできるような代替法が将来的に開発されれば、医薬品の開発等は相当な効率化が図れるだろう。
だがそのためには代替法の有効性と安全性について、長い時間をかけた、極めて慎重な比較研究等が必要になるだろう。
そのような研究の進展と規制への適用について、興味を持ちつつ見守っていきたい。
参考文献
・S. Reardon “Beyond lab animals”, (2025/8/14), Science HP
(https://www.science.org/content/article/u-s-wants-phase-out-animal-research-are-alternatives-ready)
・“Alternative Methods Accepted by US Agencies”, national Toxicology Program HP
(https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/niceatm/accept-methods)
・佐藤健太郎「第128回 動物実験がなくなる?医薬品開発における現状と廃止に向けた取り組み」(2025/6/5)薬にまつわるエトセトラHP
(https://yakuyomi.jp/knowledge_learning/etc/03_130/)
ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔