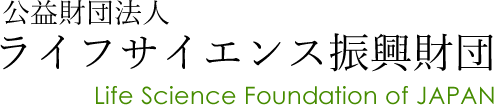第80回 AIを用いた高感染性ファージの作出
1.はじめに
米国の研究者らは、最近、AIを用いて、天然のものよりはるかに感染性の高いファージを作出したとのことである。今回はこれを巡る経緯や、意義、課題等について分析・考察を行いたい。
2.ファージの人工合成について
(1)ファージとは
ファージ(又はバクテリオファージ)とは、ウイルスの中で、細菌(バクテリア)に感染するウイルスのことである。細菌の細胞内で増殖し、最終的に細菌を破壊して(これを溶菌と呼ぶ)次の細菌に感染していく。

(2)ファージの改変
ファージのゲノムの一部に外来遺伝子を人為的に組み込むことによって、同遺伝子を増幅させたり、同遺伝子の産物であるタンパク質を産生させたりという技術は、既に1970年代からある。これは遺伝子組換え技術といい、ファージは外来遺伝子を運ぶベクターとして、プラスミドと並び、これまで多くの研究に用いられてきた。
また、外来遺伝子ではなく、ファージの本来有するゲノム自体を改変する形質転換の試みも、これまでいろいろ行われてきた。化学物質や放射線で変異を起こしたり、ファージ本来のゲノム遺伝子を遺伝子組換えにより少し配列が異なるものに置き換えたりすること等が行われてきたが、特に、DNA合成技術によって一からウイルスゲノム全体を合成できるようになると、さまざまな遺伝子改変が行われるようになった。
ただ、目的の機能を持たせるために、ファージのゲノムのどこをどのように改変すればよいか決めるのは難しい。ファージとしての感染や増殖等の機能は、ファージ内の遺伝子の発現量や生じるタンパク質の機能、さらに他の遺伝子やたんぱく質との相互作用等が絡み合っている。このため、ファージの特定の遺伝子配列を参照とするファージの遺伝子配列に変えただけでは、同じ機能を再現することはできなかった。つまりファージのゲノム配列全体を総覧して調整していくことが必要だった。それは研究者が自分自身の経験と才覚により試行錯誤していくしかなかった。
(3)AIの利用
一方、AIモデルは既に生命科学において、DNA配列、単一タンパク質、多成分複合体の生成等に利用されている。その仕組みの多くはディープラーニングの方法を用いている。すなわち実存する多数の例を用いてAIをトレーニングすることにより、それを基に、AIに新たな生体物質の機能を推定させたり、また、新たな機能をもつ生体物質を生成させようというものである。
たとえばタンパク質の構造を推定したり、新たな機能を持つタンパク質を作出するという試みにより、2024年のノーベル賞が与えられている。(2024年ノーベル賞特集2 タンパク質の構造予測や設計を行うAIの開発者にノーベル化学賞)
しかし、AIを用いてウイルスゲノム全体の設計をするのは、遺伝子間の複雑な相互作用や遺伝子複製・制御プロセスのため、はるかに困難だった。
3.今回の研究の概要
(1)研究の方法
米国スタンフォード大学と非営利団体のアーク研究所の研究者らは、ファージの働きをAIを用いて強化することを試みた。
研究に使用されたEvo1及びEvo2は、DNA、RNA、タンパク質配列を解析したり生成したりできるAIモデルである。これらAIモデルは、既に200万以上のファージゲノムを用いてトレーニングされていたが、研究者らは「教師あり学習」と呼ばれる方法でモデルをさらにトレーニングした。それにより、いわばChatGPTが目的に応じた文章を生成するように、目的に応じたファージのDNA配列を生成できるようにしたのである。
Evoモデルを用いたファージゲノムの設計にはテンプレート、つまり目的の特性を持つゲノムを生成するための開始配列が必要だった。そこで彼らは、5,386塩基、11個の遺伝子から構成されている、比較的小さなゲノムを持つ一本鎖DNAウイルスであるφX174をテンプレートとして選んだ。同ウイルスは宿主への感染と宿主内での複製に必要な全ての遺伝要素を備えていた。そして、彼らは、特に抗生物質に耐性のある大腸菌株に感染するようなゲノムを生成することを試みた。
(2)研究の成果
こうして研究チームがφX174を基に生成したファージゲノムは数千にも及んだが、それらを評価し、塩基配列から複製・生存可能と考えられる、候補となるファージゲノムを302種類に絞り込んだ。その多くはφX174のゲノムと40%以上の塩基配列が一致していたが、中には遺伝子をコードする部位の配列が全く異なるものもあった。
そして研究者らはAIの生成したゲノム情報に従ってDNAを合成し、それをまず、ある細菌に導入してファージとして増やした後、目的とする大腸菌に感染させ、それを死滅させることができるかどうか調べた。
結果として、このうち285種類がゲノムとして複製することができた。さらにそのうち、16種類が感染した大腸菌の成長を阻害したり死滅させたりできたのである。中でも、最高性能の改変ファージEvo-φ69は6時間の感染機関で16倍から65倍の増殖率を示し、天然のφX174の1.3倍から4倍を大きく上回った。
研究チームはφX174耐性の大腸菌3株を進化させ、人工ファージの変異が複数の合成ファージ株の組換えにより細菌耐性を克服できることを確認した。現在、その論文はbioRxivで査読中である。

(ネイチャー誌HPより)
4.研究の意義
今回の研究は、AIが生命の設計図であるゲノム全体を一から創造できることを世界で初めて実証したものであり、画期的なものと言える。従来の合成生物学では既存の生命体の一部を改変することが主流だったが、この研究はAIが完全に新しい機能的なゲノムを生成できることを示した。
この技術の直接的な医療応用として期待されるのは、抗生物質耐性菌に対する治療法の開発である。多剤薬剤耐性菌の出現は医療関係者を悩ませる大きな問題だが、そのような病原菌に対し感染力の強いファージをAIを用いて作出できれば、当該細菌に感染し、溶菌するという過程を通じて耐性菌を撲滅することが可能になるかもしれない。
この研究は本格的な合成生物学を利用した、大きな成果になっている。特にウイルスを利用した病原体の撲滅研究は、いわゆるファージ療法と称して、現在黒腐病にかかったキャベツの治療実験等が進められており、医療分野、農業分野、環境浄化等の分野での応用が期待される。
5.今後の課題
ただし、まだまだ改善点はある。研究者らによると、今回のEvoモデルだけでは、目的に合ったファージの設計を一から行うことはできず、研究者が介入して適切な方向付けをし、フィルタリングをすることによってはじめて作出できるとのこと。つまり、まだまだAIモデルには技術的に改善の余地があるということである。
一方で、このブレークスルーには安全保障上の懸念も存在する。デュアルユース、つまり悪意ある目的で使用される可能性があることである。
ファージであれば、いくら改変してもヒトに感染するおそれは少ない。しかし、哺乳類のウイルスをヒトに感染させるようにしたらどうだろうか。たとえば鳥インフルエンザウイルスは通常はニワトリ等に感染し、感染した鳥の致死率ほぼ100%である。同ウイルスはヒトには感染しないが、ヒトがいったん日和見感染すると致死率は50%以上になる。
鳥インフルエンザウイルスのゲノムに変異を導入してヒトに感染させるようにするような研究は、かつてセンセーションを巻き起こし、現在ではそうした研究は制限されている。実際には、単純にヒトインフルエンザウイルスの感染に係る遺伝子を鳥インフルエンザウイルスゲノムに組み込むと、通常は病原性は弱まり、それほど危険なウイルスが生じることはないだろうという見方もある。だが、AIを用いることによってそのような感染性や病原性を同時に高める可能性が提示されることになれば、それは人類に対する大きな脅威となるだろう。鳥インフルエンザウイルスのゲノムサイズは、塩基対数で1.8万個と、ファージに比べそれほど大きいわけではないことも懸念材料である。
さらに、将来的にはよりゲノムサイズが大きい天然痘ウイルス、炭疽菌等、ヒトにそもそも感染する微生物を改変させて病原性をさらに高めることになれば、生物兵器そのものになってしまうだろう。
なお研究者によると、これまでのところEvoモデルはヒトウイルスのデータでは訓練されておらず、もし現在のモデルをヒトウイルスに適用させるためには、ウイルスのゲノムとその機能について、改めて大量のデータを基に複雑な計算処理が必要になるとのことである。
6.おわりに
AI利用の用途は最近、急速に拡大している。このようなAIの利用を規制するため日本でも本年6月、AI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)が公布された。だが同法はそもそもAI利用の円滑な推進を図ることが目的であり、AIのもたらしうるリスクとして、秘密、著作権、知財、プライバシー等は考慮されてはいるものの、(コンピュータウイルスではなく、実際の)ウイルス作出への懸念については言及されてはいない。生命科学分野でのAI利用が広がるにつけ、これ以外にも懸念される研究が出現する可能性は否定できない。もっとも、AIの生命科学利用には医薬品開発等有用な面も多く、それを推進しつついかに危険な研究を未然に防ぐか、研究の進展に遅れぬよう適切な対応が講じられていくことを期待したい。
参考文献
・K. Kavanagh, “World’s first AI-designed viruses a step towards AI-generated life”, (2025/9/19) Nature HPAI
(https://www.nature.com/articles/d41586-025-03055-y)
・A. Regalado「バクテリオファージをAIが設計、ゲノム生成時代の幕開け」(2025/9/18)MIT Technology Review
(https://www.technologyreview.jp/s/369287/ai-designed-viruses-are-here-and-already-killing-bacteria/)
・Ta Tsu「スタンフォード大学、AI設計による世界初の合成バクテリオファージを開発-天然ウイルスを65倍上回る感染力を実現」(2025/9/20)InnovaTopia バイオテクノロジーニュース
(https://innovatopia.jp/biotechnology/bio-news/66676/)
ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔