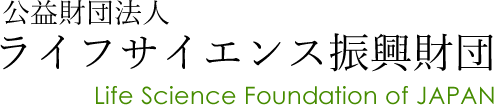第84回 ワトソン博士の功罪 ~生命の秘密の発見と人種差別~
1.はじめに
本年11月6日、ジェームズ・ワトソン博士が97歳で死去した。同博士は、フランシス・クリック博士とともに、DNAの二重らせん構造を発見し、現在の生命科学の比類ない基礎を作り、またその後も生命科学の教科書の執筆や各種プロジェクトの主導等で、まさに生命科学の巨人たる存在だった。だが、ノーベル賞を巡る画策や、二十一世紀になって起こした黒人差別問題等により、悪評を呈したのもまた事実である。
今回は、そのようなワトソン博士の業績と功罪についてレビューすることとする。なお、登場するのはもはや歴史上の人物が多く、以下、称号(博士等)は省略する。

2.二重らせんの大発見とそれを巡る画策
ワトソンは1953年に米国・シカゴで生まれた。15歳でシカゴ大学に入学、それからインディアナ大学で動物学の博士号を取得した。その後ヨーロッパに渡り、最終的には英国ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所に職を得た。ワトソンはそこで筋肉に含まれるタンパク質であるミオグロビンの研究をすることになっていた。
しかし、同研究所で、同じくタンパク質の研究を行っていたクリックと出会ったことで大きく運命が変わった。二人は、DNAの構造を明らかにすれば遺伝の仕組みが分かるかもしれないという共通の考えをもっていることを知り、本来の研究分野とは違う、DNAのモデルづくりを一緒に始めることにした。
それまで、遺伝のしくみについては、1900年に再発見・発表されたメンデルの法則により、親から子に伝えられる遺伝子というものがあるということが推測されていた。だが遺伝子の正体が何であるか、その理論とともに解明することはできていなかった。多くの科学者がその解明に心血を注いでいたが、ワトソンとクリックはそれがタンパク質や脂質などではなく、まさしくDNAであることに当たりを付けたのである。
用いたのは段ボールと金属で作られた模型だった。他の研究者の実験等から得られたことを手掛かりに、それまでに分かっているDNAの特徴を全て説明できるようなモデルを、その模型をいろいろ組み合わせることで作製しようとしたのだった。
そして1953年、彼らはついにDNAの基本構造を解明し、論文をネイチャー誌に発表した。まさに彼らは、生命の秘密そのものを発見するという、生命科学の歴史の中での最大の発見を行ったのである。

しかし、実はその発見には裏があった。彼らの発見に重要な役割を果たしたのは、「フォト51」と呼ばれる、DNAのX線結晶解析写真だった。これは当時同じ大学のキングス・カレッジで研究していた英国人生物物理学者のロザリンド・フランクリンが撮影したものだった。ところが、生物学者のモーリス・ウィルキンスが、フランクリンに内緒でワトソンとクリックにその写真を見せた。そして2人はそれを用いてDNA構造を推定し、彼女の許可なしにそれを公表したのである。

1962年に、ワトソンとクリック、それからウィルキンスの3人はノーベル生理学・医学賞を受賞した。ノーベル賞の受賞者は一つのテーマについて3人までに制限されており、また授賞発表時に存命であるという条件が付く。既に1958年にフランクリンは卵巣がんで死亡していたが、もし生きていたらどうだったろうか。だが、著者「二重らせん」の中で、彼女は敵意に満ちた意地悪な女性として書かれた。そうして、DNAの構造の発見に彼女が果たした役割に誤解をもたらしたことも否めず、彼女の功績を見下すような書き方をしたワトソンに対し、激しい批判も起こった。
3.数々の業績
ワトソンはその後、米国ハーバード大学の教授となり、15年間在籍した。その間に、研究においては、DNAから遺伝情報を写し取るメッセンジャーRNAの発見に貢献する等の成果を挙げたが、彼の業績は研究のみにとどまらなかった。ハーバード大在籍中に、「遺伝子の分子生物学」を書きあげた。これは生命科学の教科書として世界中で用いられた。
1968年からは、米国ニューヨーク州のコールド・スプリング・ハーバー研究所(CSHL)の所長を兼任した。当時、同研究所は財政難に陥っており、施設はボロボロで、組織もしっかりしていなかった。だが、ワトソンは自分の名声や人脈を利用して多額の研究費や寄付金を引っ張ってきた。そして同研究所はがん研究、神経生物学、ゲノミクス等生命科学の世界有数な研究機関になった。
4.ヒトゲノムプロジェクトへの貢献
ワトソンは1990年、CSHL所長のままで国立衛生研究所(NIH)のヒトゲノム研究センターの初代所長を兼務し、ヒトゲノムプロジェクトの責任者に任命された。だがその後、彼はNIHの所長バーナディン・ヒーリーと対立した。ヒーリーは、当時前例がなかった遺伝子配列の特許を取得することに積極的だった。これに対し、ワトソンは、ヒトゲノムは世界の人々のものであるとして反対した。結局ワトソンは、1992年4月にNIHを去り、CSHLに戻った。なお後任には後にNIHの所長を務めたフランシス・コリンズが任命された。
ヒトゲノムプロジェクトについてのワトソンの指導的役割はそこまでだったのだが、ヒトゲノムプロジェクト終了後の2007年、民間企業が中心となってワトソン自身のゲノムを解読・公開した。個人のゲノムが解読されたのは、ヒトゲノムプロジェクトに対抗してヒトゲノム解読を行ったセレーラ・ゲノミクス社のクレイグ・ベンターのゲノムに次いで二番目となった。
5.人種差別と悪評
高名だったワトソンに悪評が立ったのは、二重らせんの発見から半世紀以上たってからだった。ワトソンは2007年、英国のタイムズ誌に、「自分は、アフリカの将来について悲観的だ。我々の社会政策は、彼らの知能が我々と同じだという事実に基づいているが、全ての実験結果はそうでないことを示しているからだ。」と語った。つまりアフリカ人は知能が低いと明言したのである。ワトソンは純粋に遺伝学的見方からそう話したのかもしれないが、これは社会的にも大きな批判を招いた。そしてワトソンは同年、CSHLの職を辞さざるを得なくなった。
ワトソンは贖罪のためか、ノーベル賞のメダルをオークションにかけた。ワトソンはその収益金410万ドルを慈善団体に寄付した(なお落札したのはロシアの大富豪だったが、落札後すぐにそれを本人に返したとのこと)。また、国立衛生研究所(NIH)における倫理局の設立に貢献し、強制不妊手術など国による優生政策を批判した。
ワトソンは2008年、CSHLの名誉総長に任命された。しかし、同氏の、黒人や女性について、科学的根拠のない発言を繰り返す傾向は変わらなかった。このため、2019年にはついにCSHLから名誉称号を剥奪され、CSHLとの関係は断たれた。
こうしたワトソンのことを、ある学者は「二十世紀で最も重要で最も有名な科学者であると同時に、二十一世紀で最も悪名高い科学者でもあった。どちらの場合も、その理由は彼の遺伝決定論にある。」と評している。
4.おわりに
以下、著者の個人的感想である。
著者が就職したのは今から40年前の1985年のことである。私は学生の頃「二重らせん」を読んで生命科学の世界に大いに魅了されたが、研究者になる夢は叶わず、大学院の修士課程終了後、行政の世界に入った。
その当時、入庁したての私の指導を行ってくれていた年配の研究者がこんなことを話した。「ワトソンとクリックは、二重らせんを発見したことで、ともに偉大な研究者であることに変わりはない。しかし、その後の業績を考えると、クリックは研究者としてだけ活動を続けているが、ワトソンは教科書を書いたり、各種のプロジェクトを起こしたり、啓蒙活動や若手の指導・教育という面で、人間としてのすそ野はものすごく広がった。」とワトソンを賞賛した。その頃既にワトソンは伝説的人物となっており、また人種差別発言のはるか前のことだった。私はなるほどと思い、研究者は、研究だけでなく、後進を育てるというのも重要な役割なのだなあと思った。
しかし、スポーツの世界の諺「名選手必ずしも名監督ならず。」は科学界にも当てはまるかもしれない。ノーベル賞受賞者が、受賞後、いきなり政府の審議会の委員に選任されたり、大学の学長になったりすることがある。だが、それまで研究に専念してきた研究者には、行政業務や管理業務に慣れていない場合もある。行政や管理においては、研究のように自分のやりたいこと、人とは違うことを自分の責任でやっていくのではなく、関係者の意見や周囲の状況を十分踏まえたうえで進めていかねばならない。このため戸惑うことがあるだけでなく、思い込みがかえって悪い結果を招くことがある。また行政に時間をとられて自身の研究を十分に進めていくことができなくなるかもしれない。
私としては、そうした研究者は、むしろ行政とかかわりなく、十分な資金を提供した上で、得意な研究を続けていってもらいたいと思う。もちろん、すぐれた研究者のほとんどは、行政能力や調整能力を兼ね備えているのは間違いないことではあるが。
参考文献
・J. Witcowski, “James Watson obituary: co-discoverer of DNA’s double helix who reshaped modern biology” (2025/11/13) Nature HP
(https://www.nature.com/articles/d41586-025-03761-7)
・J. Cohen (2025) “James Watson: A flawed titan of science”, Science; Vol.390, 664-665
・「DNAの二重らせん構造を発見したワトソン氏が死去、その光と影」 (2025/11/15) ナショナル・ジオグラフィック日本版HP
(https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/25/111300624/)
ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔