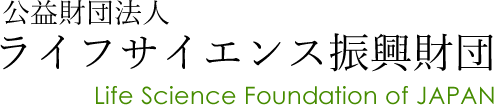第81回 2025年ノーベル賞特集 制御性T細胞を発見した坂口博士ら3人にノーベル生理学・医学賞
1.はじめに
2025年のノーベル医学・生理学賞に、制御性T細胞を発見した大阪大学の坂口志文(さかぐちしもん)特任教授(医学博士)ら3人が選ばれた。その内容や背景、意義等について考察する。
2.受賞者と授賞理由について
今回受賞したのは大阪大学の坂口志文博士、米国のバイオ企業ソノマ・バイオセラピューティクス社のブラッド・ラムズデル博士、米国システム生物学研究所のメアリー・E・ブランコウ博士の3人である。
授賞理由は「末梢免疫寛容に関する発見」すなわち制御性T細胞により、免疫の過剰な働きを抑える仕組みの発見である。
彼らは1,100万スウェーデン・クローネ(2025年10月時点で1クローナは約16円であるので、約1億7,600万円)の賞金を分け合うことになった。

3.免疫の仕組みと制御性T細胞について
(1)免疫の仕組み
まず免疫の全体像について簡単に説明する。
免疫とは体に侵入した病原体(ウイルス、細菌等)や、体にできたがんなど異常な細胞等を異物として認識し、それらを撃退することによって、体を病気から守る働きである。
免疫システムは、大きく分けて、自然免疫と獲得免疫という、2つの仕組みからできている。
自然免疫は、普段から体の中で監視を行っており、体に異物が侵入したりできたりすると、真っ先にそれを見つけ、撃退する役割である。この仕組みを担っているのは、マクロファージや好中球などで、これらにより病原体(ウイルス・細菌)等、普通の異物は撃退される。
一方、獲得免疫は、自然免疫だけでは撃退できないとき、少し遅れて働くシステムで、高等生物のみに備わっている。自然免疫で働いたマクロファージや樹状細胞等が、ヘルパーT細胞等の免疫細胞に通報したり、吸収した異物の一部を抗原として外部に提示したりすることで、B細胞や、キラーT細胞を増殖させる。B細胞は病原体等の異物に特異的な抗体を産生する体液性免疫として働き、キラーT細胞はウイルス感染細胞やがん細胞に特異的に攻撃する細胞性免疫として働く。

(2)制御性T細胞について
それでは、今回の受賞対象となった制御性T細胞とはどのようなものか。
獲得免疫にかかわる細胞のうち、ヘルパーT細胞やキラーT細胞といったT細胞は、心臓の近くの胸腺(thyms gland)で作られ、成熟する(一方、B細胞は骨髄(bone marrow)で作られる)。作られたT細胞のうち、正常に機能できない不良品のT細胞は、成熟後、大部分は胸腺内で壊される。だが、一部は壊されないで生き残り、それは正常な細胞を攻撃したり、他の免疫細胞に攻撃を指示したりするようになってしまう。これは体にとってよくないことである。このため、これらのT細胞を標的として、その働きを抑える仕組みがある。それが制御性T細胞である。
こうした、免疫を制御する細胞の研究は1970年代には盛んに行われたが、その存在がなかなか検証できず、1980年代には下火になっていった。それに光を当て、制御性T細胞を特定したのが今回のノーベル賞の研究である。
4.受賞者らの研究について
この3人のうち、制御性T細胞自体を発見したのは坂口博士である。同博士は、マウスの胸腺を摘出し、正常なマウスのT細胞を補ったところ、生じていた自己免疫疾患の症状が全く起こらなくなることを発見した。このことから同博士は、胸腺では、T細胞だけでなく、不良品のT細胞の暴走を抑えるブレーキ役の細胞も作られていると考えた。そして、胸腺に含まれている細胞を、表面に発現するマーカーを目印に調べていったところ、CD25というマーカーで同定できる細胞が免疫反応を抑えているということを突き止めた。T細胞の中に10%ほど含まれる、CD25をマーカーとする細胞をマウスから取り除くと甲状腺、膵臓その他の臓器で自己免疫疾患を発症し、その細胞を戻すと症状が治まったのだった。そして1995年、坂口博士はその結果を発表し、その細胞を免疫反応を制御するという意味で、制御性T細胞(Tレグ)と名付けた。
この発見により、研究者は初めて制御性T細胞を分離して研究できるようになった。そして他の研究チームは、異なる種類の免疫細胞を持つ異なるタイプの制御性T細胞を研究・特定するようになっていった。
一方、2000年代初頭になって、ラムズデル博士とブランコウ博士は坂口博士の発見を基に、特定のマウス系統が自己免疫疾患に特にかかりやすい理由を解明した。両氏はマウスに遺伝子変異があることを発見し、これをFoxp3と名づけた。さらに、ヒトにおいてこの遺伝子の変異が重篤な自己免疫疾患であるIPEX症候群を引き起こすことを明らかにした。
坂口博士は2003年に、この研究結果を自身の研究と結び付け、FOXP3遺伝子が制御性T細胞の発達を制御していることを証明した。
5.本研究成果の意義・方向性
今回のノーベル賞受賞者たちの研究により、免疫系がかつて考えられていたよりもはるかに複雑であることが分かったことで、その後の研究の進展に果たした役割は大きい。
そして、制御性T細胞については、その働きを弱めたり強化したりすることで、今後、大きな医療応用の可能性を秘めている。
まず、1型糖尿病、狼瘡、関節リウマチ、多発性硬化症等の自己免疫疾患の治療への利用である。これらは免疫が強すぎる患者で見られる疾患であり、患者は血液中の制御性T細胞が不足しているか、正常に機能していないことが分かっている。このため制御性T細胞の働きを強化することで免疫系のはたらきを抑え、これら疾患の治療につながることが期待される。
マウスを用いた初期の実験では、制御性T細胞をこれらの疾患の治療に利用できる可能性が示されている。米国イーライリリー社やセルジーン社などの大手製薬会社は、制御性T細胞を刺激する薬剤に投資しており、1型糖尿病、自己免疫性肝炎等の治療法が現在臨床治験中である。
免疫系を弱めた方がよい場合は他にもある。臓器移植である。自己のものではない臓器は移植された患者に激しい拒絶反応をもたらす。しかし患者の制御性T細胞のはたらきを強化することによって免疫系の働きを弱めることができれば、移植後も免疫抑制剤等を使用し続けることがなくなるかもしれない。
一方、制御性T細胞の働きを抑えることで、免疫系がより働くようにすれば、病原体に対する抵抗力を強められるかもしれない。また、体内で生じた異常な細胞は通常、免疫のシステムにより異物として撃退されるが、中には免疫をかいくぐって自己増殖を続けるものもあり、結果的にそれらががんになると考えられる。そこで制御性T細胞を抑制することで免疫系を強化してがん細胞を撃退することが期待される。ただし、これらについては臨床応用はこれからであろう。
6.おわりに
日本はライフサイエンス分野の中では特に免疫系が強いことは以前から言われてきたが、今回の坂口氏の受賞はそれを裏付ける形となった。
これまでのノーベル医学生理学賞の受賞者(利根川進氏(1987年)、山中伸弥氏(2012年)、大村智氏(2015年)、大隅良典氏(2016年)、本庶佑氏(2018年))と合わせると、利根川、本庶、坂口氏と、6人中半分の3人は免疫の研究者である。なおこれ以外に、2011年のノーベル生理学・医学賞の対象となった自然免疫について、対象論文の共同著者だった大阪大学の審良静男特任教授のように限りなく肉薄していた研究者もいた。今後もこの分野の発展に期待したい。
2001年に策定された第二期科学技術基本計画では今後50年間でノーベル賞30人という目標が掲げられた。当初は無謀に思えたこの目標も、その後の受賞ラッシュにより、目標達成も十分現実的を帯びてきている(2001年以降25年間で21人)。今回受賞対象となった坂口氏の論文発表は1995年で、くしくも科学技術基本法の制定年である。
同法や科学技術基本計画に伴い、その後の研究への資金の出し方や研究者へのサポート体制も大きな方向転換が図られたが、ただ、明確にそれ以降の研究で受賞したといえる研究者は山中博士等わずかであり、はたしてその方向転換が正しかったかどうかは分からない。今後、引き続き注視していきたい。
参考文献
・M. Naddaf et. al. “Medicine Nobel goes to scientists who revealed secrets of immune system ‘regulation’, (2025/10/06) Nature HP
(https://www.nature.com/articles/d41586-025-03193-3)
・J. Gallagher, “Scientists win Nobel Prize for discovering why immune system does not destroy the body”(2025/10/6)BBC HP
(https://www.bbc.com/news/articles/c2knwvpd7vno)
・藤川良子(2017)「制御性T細胞研究とともに歩む」natureダイジェスト; Vol.14 No.10
・「坂口氏ノーベル賞」(2025/10/7)読売新聞
・かねしろ整形外科リウマチクリニックHP(図として利用)
(https://kaneshiro-ra.com/kaneshiro/rheumatic-disease/immunity)
ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔