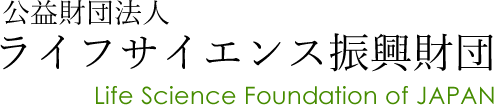第48回 ヒトiPS細胞から精子と卵子の元になる生殖細胞を作出
1.はじめに
京都大学の研究者らは、ヒトのiPS細胞から精子と卵子の元になる生殖細胞を作出することに成功し、本年5月、Nature誌に発表した。今回はこの記事について、背景・経緯、研究内容、意義、課題等について考察する。
2.研究の背景・経緯
今回の研究について述べる前に、体内でヒトの生殖細胞ができていく過程を説明する。
まず受精から2週間後、胚発生の過程の中で、精子や卵子の大元の細胞である「始原生殖細胞」ができる。そして受精6~10週後になると、男の胎児の精巣では「前精原細胞」、女の胎児の卵巣では「卵原細胞」にそれぞれ分化する。
それらは分裂を繰り返し、最終的には男の場合、誕生後に精母細胞を経て精細胞、さらに精子になる。また女の場合、誕生後に卵母細胞を経て卵子(卵細胞)となる。

これらの生殖細胞を人工的に作出すべく、これまで様々な試みがなされてきた。その方法としては、主にiPS細胞や胚性幹細胞(ES細胞)に化学物質やホルモン等を与えることで精子や卵子を直接作出する方法や、又はその元となる細胞を作出し、それを分化させて精子や卵子にする方法が考えられた。
既にマウスにおいては、iPS細胞からの生殖細胞づくりは進展している。京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)の斎藤通紀教授(拠点長)らのグループは、2011年、マウスのiPS細胞から精子を作り、その精子を普通の卵子と受精させて仔マウスも誕生させた。
またその後2015年には、マウスのiPS細胞から卵子を作り、それから仔マスも誕生させたことを報告した。これらは当時、世界初の快挙だった。
さらに、大阪大学の林勝彦教授のグループは2023年、雄のマウスのiPS細胞から卵子を作り、別のオスの精子と受精することで、オスのマウスだけから子供を誕生させた。(第21回ニューズレター参照)。
一方、ヒトではこのような研究は難しかった。同様の方法をヒトのiPS細胞で試みてもうまくいかなかった。
ヒトの生殖細胞の分化過程はマウスより複雑で、詳細な知見が不足していた。
また上述のように、生殖細胞の卵子や精子への分化は、胚から胎児、さらに誕生後にわたって行われる。しかしそのようなヒト胚や胎児は研究で扱うことは倫理的に難しいことも障害になっていた。
斎藤教授らは、2015年に、ヒトのiPS細胞に薬剤等を加えて「初期中胚葉様細胞」と呼ばれる細胞を作製し、さらにその細胞にある種のタンパク質を作用させることにより、PGC様細胞(PGCLCs)という、始原生殖細胞(PGC)に似た細胞を高い効率で作出したことを発表した。
そして2018年には、ヒトPGC様細胞をマウスの胎仔から取り出した卵巣細胞と混ぜて培養することでヒトの卵原細胞も作出した。ただ、できた卵原細胞は少なく、たとえば5,000個の始原生殖細胞から作られる卵原細胞は約500個にとどまり、作業効率が低かった。また、作製時にマウスの細胞に頼らなければならないことも課題だった。
3.今回の研究の内容
斎藤教授らは、上述のヒトPGCLCsに、ヒトの体内にあって骨など体の形成を促すタンパク質の一種であるBMP2を投与した。すると約2か月後、ヒトの生殖細胞の一つであるヒト卵原細胞とヒト前精原細胞が作出された。さらに、染色体数を安定させて約4か月培養したところ、細胞数は当初の数に比べ、100億倍にも増えたとのことである。
生殖細胞には、体内で作られる過程で「エピゲノムリプログラミング」という現象が起こる。エピゲノムとはメチル化等のゲノムの修飾のことであり、身体の各器官や組織に応じてゲノムのいろいろな部位が修飾されることにより、それに対応した遺伝子が発現し、それぞれの働きがなされる。
エピゲノムリプログラミングでは、生殖細胞が作られる過程で、ゲノム修飾がされていない状態に戻り、それまで修飾により蓄積されてきた情報がリセットされる。これは生命の誕生における重要な反応だが、これまで詳しいことは分かっていなかった。
今回の研究では卵原細胞等の作出過程でエピゲノムリプログラミングも再現され、その仕組みの一端が解明できたとしている。
ただし、今回の実験ではリプログラミングの後、細胞の分化は停止し、前精原細胞や卵原細胞の先の分化は起こらなかった。また、作出された前精原細胞や卵原細胞について、エピゲノムの修飾の大部分は消去されたものの、いくつかは残っていることも分かった。

4.研究の意義
今回の研究では、iPS細胞から前精原細胞や卵原細胞を、たった1つのタンパク質を添加するという簡単な方法により作製することができた。
従来は、始原生殖細胞から先の生殖細胞を作るには、前述のように特殊な技術を使う必要があり、またその作製効率も悪かった。
今回、そうしたハードルを越えたことで、それから先の生殖細胞作りに拍車がかかると考えられる。またこれら生殖細胞を大量に作製できるようになったことも意義がある。
前精原細胞や卵原細胞は体内でも数が限られており、その挙動や性質の研究はかなり難しかった。だが、目的の細胞が大量にあることで、実験がしやすくなり、研究の進展が期待される。
そうして得られた知見は、不妊症や、先天的な病気の原因解明や治療法の開発に役立つと期待される。
たとえば、患者本人の精子や卵子を使うのでなく、作出された精子や卵子を用いて、疾病の原因となるDNA配列をゲノム編集により修復するという研究もできる。そうすれば、精子と卵子が合体して作られた胚でゲノム編集を行うよりも、より容易に疾病の原因を解明・除去できるかもしれない。
5.研究の課題
(1)技術的課題
卵原細胞や前精原細胞はヒトの体内ではさらに何段階か変化して卵子や精子に変わるが、現在の研究ではまだその段階は再現されていない。そのためには、前述のような前精原細胞や卵原細胞で停止した分化過程を再開させねばならない。
また、それとも関連するが、作出された精原細胞や卵母細胞について、前述のようにエピゲノムリプログラミングが不完全である可能性がある。そのような生殖細胞が実際に使用された場合、それから作出される胎児に深刻な結果をもたらす可能性があり、その原因を解明・改良していく必要がある。
(2)倫理的課題
倫理的側面はどうか。将来、iPS細胞などからヒトの精子や卵子が作ることが技術的に可能になったとしても、それを実際に生殖に使うかどうかは様々な観点で議論が必要である。
少なくとも現在、国際幹細胞学会(ISSCR)のガイドラインでは、ヒト幹細胞から分化させた配偶子(生殖細胞)の生殖利用については、現時点では安全ではないとして容認されないという分類になっている。だが安全性の問題だけではない。そもそも人工合成された生殖細胞を通常の生殖細胞と同様の位置づけで扱うべきか否かという問題がある。また、そのような生殖細胞にゲノム編集等の改変を行う場合も、どこまで許容されるかという問題がある。病気を予防するための改変は、知能や運動能力に関連する形質を高めるための遺伝子強化につながる可能性もある。
日本では、ヒトの卵原細胞などの生殖細胞をつくる研究は2010年に国(文部科学省)の指針が整備されて可能になった。だが、ヒトiPS細胞やES細胞からできた卵子と精子で受精卵やヒト胚を作製することは引き続き禁止されている。ただ、この分野は研究の進展が速いため、それに迅速に対応すべく、その時点での技術的・倫理的知見を最大限に活用して議論を行わねばならない。
こうした生命倫理に関する問題については、内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の生命倫理専門調査会が、さまざまな課題について幅広く議論してきている。たとえば、CSTIの報告に基づき、2021年には、受精卵から核を取り出し、それを核を抜いた他人の受精卵に移植する「受精胚核置換」をミトコンドリア病に関する基礎研究に限って可能とするように文科省の指針が改正された。
また、ヒトiPS細胞などを使ってヒトの受精卵(胚)を再現した「胚モデル」(第34回ニューズレターで紹介)については2022年から検討を行ってきているが、今年3月には、その人体内への移植は科学的合理性がなく倫理的も許容されないとして禁止し、引き続きヒトの命の誕生につながる研究を制限すべきだとの見解を生命倫理専門調査会の下部組織である作業部会が報告した。
一方、今年1月には、同調査会委員からのアンケート結果も踏また審議を行い、ヒトのiPS細胞等から人工的に作製した卵子や精子について、それを受精させる基礎研究については容認する意見が多数を占めた。今回の研究成果は今後の生殖医療を進展させる可能性が高く、同調査会では具体例な研究進展例として議論で取り上げられることになると思われる。
6.おわりに
日本は世界に先駆けてiPS細胞の作出を行ったものの、その後、同細胞を用いた再生医療研究については各国が追随し、激しい競争が行われている。
そのような中、iPS細胞からのヒト生殖細胞の作出研究においては日本での画期的な研究例が多く、世界を先導しているといえる。
こうした競争力を維持していくためには、倫理的にも十分配慮した上で必要な規制を整えていくことも必要だと思われ、著者としては研究面と規制面の協調的な発展を今後も見守っていきたい。
参考文献
・H. Ledford (2024) “‘Epigenetic’ cell reset paves the way for lab-grown sperm and eggs”, Nature; Vol.629, s984
・内城喜貴「ヒトiPS細胞から卵子と精子のもとを大量作製 京大、生殖医療研究進めるも倫理上の議論必要」日本科学技術振興機構 Science Portal(2024/05/2(https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20240522_g01/index.html)
・「ヒトiPS細胞から前精原細胞及び卵原細胞を大量誘導―ヒト生殖細胞試験管内造成研究のマイルストーン―」ASHBi(https://ashbi.kyoto-u.ac.jp/ja/news/20240521_research-result_saitou/)
・H. Ledford (2024) “‘Epigenetic’ cell reset paves the way for lab-grown sperm and eggs”, Nature; Vol.629, s984
・内城喜貴「ヒトiPS細胞から卵子と精子のもとを大量作製 京大、生殖医療研究進めるも倫理上の議論必要」日本科学技術振興機構 Science Portal(2024/05/2(https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20240522_g01/index.html)
・「ヒトiPS細胞から前精原細胞及び卵原細胞を大量誘導―ヒト生殖細胞試験管内造成研究のマイルストーン―」ASHBi(https://ashbi.kyoto-u.ac.jp/ja/news/20240521_research-result_saitou/)
・Try IT 高校生物(図として引用)(https://www.try-it.jp/chapters-15192/sections-15193/lessons-15235/point-2/等)
ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔