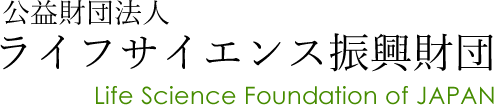第69回 マウスの詳細な脳地図が作製される
1.はじめに
米国の研究者らは、これまでで最も詳細なマウスの脳地図を、視覚皮質について作製・解析し、今年4月、ネイチャー誌やその系列誌に多くの論文として発表した。今回はこのことについて、背景や意義等も含めて分析・考察を行う。

2.脳地図とは
脳地図(Brain Map)とは、脳に存在する神経細胞(ニューロン)や接合部位(シナプス)の位置関係を明らかにしたもので、それを作製することをマッピングという。
脳地図のうち、特にニューロン同士のつながり、つまり配線図を示すものをコネクトームと呼ぶ。脳のコネクトームや、刺激に対する発火状況を調べることにより、信号が脳内をどのように流れ、それが認知、思考、学習、行動といったさまざまな脳の働きにどうつながるのか解明されることが期待される。

3.これまでの脳の地図化の歩み
脳は生命科学分野で人類に残された最後のフロンティアと言える。
生命科学は、ワトソン・クリックの「二重らせん」の発見以降、急速に進展してきた。特に21世紀初頭のヒトゲノム解読の完成、さらにそれに続く各種オミックスの進展により、細胞や組織、器官、生物個体中の必要な情報は全て入手することができ、あとはそれを解析していけばよいだろうという風潮にもなってきた。
ところが、脳は一筋縄ではいかない。脳のニューロンは他のニューロンと結びつき、回路を形成することにより、認知、思考等、さまざまな脳機能を発揮するようになる。しかし、回路は実に複雑で、その観察は難しい。つまり脳の詳細な情報の入手そのものが困難であった。また、たとえ情報を入手したとしても、解析にはさらに、たいへんな労力が必要になる。特定のニューロンに絞って回路を特定するとか、あるいは大雑把にどのような神経がつながっているかを調べることはある程度可能だった。
だが、ニューロンのつながり全体を網羅的に調べる場合、ニューロンの数が増すに従ってつながるニューロン同士の順列組み合わせが等比級数的に増大し、狭い空間に高密度で回路が存在するようになり、観察や解析の困難さが増す。
そのようなことから、先述のクリック博士は、1979年に「1立方ミリメートルの脳組織とその中のすべてのニューロンがどのように発火するかの正確な配線図を作製することは不可能だ」と断言した。
しかし、そのような考え方を乗り越えるべく、脳の研究者らは努力を重ねてきた。方法として、いきなり複雑なヒトの脳等を解明するのは困難であるため、まずは脳の作りが簡単でわかりやすい下等生物から解析を始めていき、次第により高等な生物にシフトしようとした。また、コネクトームの測定や解析を一つの機関の一人の研究者だけで行うのではなく、複数の機関の多くの研究者の協力により、互いに知恵を出し合いつつ共同作業を行ってきた。
その結果、2019年になって漸く、約300個のニューロンをもつ線虫の全コネクトームが解明された。その後、2023年には約3,000個のニューロンをもつ昆虫(キイロショウジョウバエ)の幼虫の脳のコネクトームが作製され(第20回 史上初の昆虫の脳の完全なマッピングが完成)、さらに昨年10月には、約14万個のニューロンをもつショウジョウバエの成虫のコネクトームが作製された(第56回 ハエの脳全体の神経回路地図を完成)。
研究者らの最終的なターゲットは、ヒトの脳のコネクトーム作製である。しかしヒトの脳は約860億個のニューロンがあり、ショウジョウバエ成虫のなんと60万倍もある。それを一足飛びに作製するのは極めて困難である。そこで研究者らが次のターゲットにしたのは、ショウジョウバエ成虫の約30倍、400万個のニューロンを持つマウスだった。
4.今回の研究の手法と成果
(1)MICrONSコンソーシアムについて
「皮質ネットワークからの機械知能(MICrONS:Machine Intelligence from Cortical Networks)」コンソーシアムは、脳のアルゴリズムをリバースエンジニアリングすることで、機械学習に革命を起こすことを目指し、7年前に設立されたプロジェクトである。米国アレン研究所、プリンストン大学、ハーバード大学、ベイラー医科大学、スタンフォード大学など、多数の大学の150人を超える研究者が参画している。
リバースエンジニアリングとは、エンジニアリングが図面や設計情報をもとに部品・製品を生産するのに対し、逆に既存の製品を分解または解析し、その構成部品や仕組み、技術や設計などを明らかにすることである。MICrONSは、まさにブラックボックスである脳、特にニューロンが集中している皮質における配線を調べることで、その働きを解明していくことを目指している。
なお本研究の実施に当たっては、米国の脳のビッグプロジェクトであるBRAINイニシアチブのほか、国家情報長官室(ODNI)の研究開発部門であるインテリジェンス高等研究計画活動(IARPA)からも資金が拠出されている。
(2)今回の研究の方法
マウスの脳地図を作製するために、各機関の研究者たちは、実験段階毎に役割分担をして作業を行った。
まずベイラー医科大学の研究者らは、マウスに、さまざまな映画やYouTubeの動画等を視聴させた。そして、特殊な顕微鏡を用いて、その際の視覚皮質における約7万5,000個のニューロンの発火状況を記録した。
次に、アレン研究所の研究者らは、上記の実験を行ったマウスの脳を1立方ミリメートルの大きさに切り分け、ヒトの髪の毛の約400分の1の幅を持つ2500枚以上の極めて薄い組織切片を作製した。
そして、プリンストン大学の研究者らは、電子顕微鏡で各切片を撮影し、それらの画像を、3次元再構成技術を用いて地図にまとめた。そして、AIと機械学習アルゴリズムを用いて、各ニューロンやシナプス等に注釈を付ける作業を行った。
(3)今回の研究の成果
今回の研究を通じ、哺乳類としてはこれまでで最も詳細な脳地図が作製された。
視覚皮質に存在する20万個の細胞(うち8万2,000個がニューロン)と、それを結び付ける5億2,300万に上るシナプス、総長4キロメートルに及ぶ軸索の詳細な地図に加え、マウスが多様な視覚刺激を受けた際に記録された約7万5,000個のニューロンの機能画像が提示された。
本研究を通じて、ニューロンの機能に基づいた普遍的な配線規則が明らかにされるとともに、理論を検証するためのデジタルモデルが開発され、新規刺激に対する脳の反応を予測するアルゴリズムも作製された。
また、異なるニューロンのタイプを構造に基づいて分類する方法や、遺伝子発現データとニューロンの接続パターンとの関係についての分析・考察がなされた。さらに、大規模な電子顕微鏡による再構築データの解析と自動校正を可能にする新たなツールについても報告された。
本研究による特に大きな発見として、脳内の新たな抑制原理の発見が挙げられる。脳には、抑制細胞という、神経活動を抑制する細胞があるが、それは従来、他の細胞にランダムに作用してそれらの活動を弱める単純な働きであると考えられていた。しかし、本研究により、抑制細胞は、どの興奮性細胞を標的とするかを特異的に選択することで、ネットワーク全体にわたる調整と協力のシステムを構築する機能も持つことが分かった。
(4)今回の研究の意義
今回解析が行われたニューロンやシナプス等はすべて、視覚に関わる脳領域の小さな組織ブロックに存在している。つまり、極めて微小かつ高密度のものである。さらに、それは視覚情報を処理するために信号を発し、相互作用する数万個のニューロンの活動も捉えている。
先のクリック博士の言葉のように、このようなことが可能になるとは、しばらく前までは考えられなかった。今は脳の中の視覚皮質のみだが、脳の他の部位もほぼ同じ密度でニューロンやシナプスが存在しているとすれば、今回の研究を物理的に拡張していけばマウスの全脳での地図作りも可能になるだろう。
そうするとどうなるか。現在得られた成果だけでも、抑制細胞の新たな働きやネットワーク全体の協調など、脳組織の驚くべき原理が明らかになった。これが全脳に拡張した場合、脳機能、知能、神経疾患等の研究の進展への貢献は計り知れない。
そして、いったん正常な脳の配線図が分かれば、各種脳疾患において、配線のどこが異なるのかを比較し、原因を究明することが期待される。
その先にはヒトの脳地図作りが見えてくる。人間の脳の1立方ミリメートルには1万6,000個のニューロンと1億5,000万個のシナプスが含まれている。脳全体の大きさを考えると、まだまだその解明は先にあるだろうが、少なくとも解明のための有力な土台はできたように思える。
MICrONSプロジェクトは、そのリソースつまり配線図やデータを神経科学コミュニティ向けにオンラインで無料公開している。その量は1.6 ペタバイトにもなり、他の研究者にとってはまたとない研究のプラットフォームとなる。
5.おわりに
前述のように脳は生命科学上の最後のフロンティアであるだけに、その解明を巡る競争は激しい。しかしそのような中でも各機関が協力することで急速に解明が進んでいる。またその成果が共通のプラットフォームになりつつあるのも望ましい。
なお日本も脳についてはビッグプロジェクトがあり、マーモセット等を対象として各種解析が行われているが、ぜひともその成果を期待したい。
また、脳研究の進展に伴い、生命倫理の問題や、AIとの比較やAIへの適用等の問題もますますクローズアップされてくると思われる。今後もフォローしていきたい。
参考文献
・M. Naddaf, “Biggest brain map ever details huge number of neurons and their activity”, (2025/4/9) Nature HP
(https://www.nature.com/articles/d41586-025-00908-4)
・M. Barnhart, “World’s Most Detailed Brain Map Built From a Grain of Brain Tissue”, (2025/4/9) Neuroscience news com. HP
(https://neurosciencenews.com/brain-wire-mapping-28583/)
・S. Lyon, “Scientists map the half-billion connections that allow mice to see”, (2025/4/9) Princeton University HP
ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔