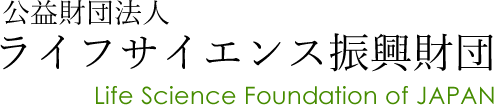第70回 パーキンソン病に対する幹細胞治療が進展
1.はじめに
京都大学医学部附属病院とiPS細胞研究所(CiRA)は、今年4月、ヒトの人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作製された神経細胞をパーキンソン病患者に移植した臨床試験の結果をネイチャー誌に発表した。それによると、被験者のかなりの割合に症状の改善が見られたことが分かった。
今回はこれについて、幹細胞治療を巡る状況も含め、分析・考察を行う。
2.パーキンソン病について
パーキンソン病は、神経伝達物質であるドーパミンを作る神経細胞が減少することにより発症する難病である。ドーパミンは脳内で運動の調節に関わっており、この減少により手が震えたり、体が動かなくなったり、歩行が困難になったりする。国内患者数は推計29万人、世界では1,000万人を超える。50歳以上で発症することが多く、65歳以上では100人に1人程度が患っているとされる。
治療法としては、脳でドーパミンに変わって足りていないドーパミンを補うレボドパという薬や、ドーパミン受容体に刺激を与えることでドーパミンが出たのと同じ状態にするドーパミンアゴニストという薬がある。また、電極を脳に埋め込むといった治療法もある。
それらにより症状はある程度抑えられるが、対症療法的であり、現段階ではドーパミンを産生する神経細胞を増やす等の根本的な治療法は開発されていない。
3.iPS細胞を用いた幹細胞治療の進展
iPS細胞を用いた幹細胞治療研究の進展状況をざっと紹介する。特に本分野は日本が主導しているため、日本の状況を中心に述べる。
iPS細胞は京都大学の山中伸弥博士が2006年に作出した細胞で、基本的には生体中のあらゆる組織に分化できる。iPS細胞は、同様な性質を持つ胚性幹細胞(ES細胞)と比べ、作出の際にヒト胚を破壊しないため、倫理的な問題が少ない。また、治療を必要とする患者自身の細胞から作製できるため、それから分化させた組織や器官を患者本人に移植しても拒絶反応は起こらず、免疫抑制剤を必要としない。
そのような利点があるため、iPS細胞の治療への適用を目指し、その発見初期から研究が行われてきた。最も早く臨床試験が行われたのは目の網膜疾患で、当時理研にいた高橋政代博士が2014年に世界で初めて実施した。
その後、今回のパーキンソン病をはじめ、心疾患、脊髄損傷、糖尿病、肝疾患、腸疾患、関節病等、さまざまな疾患に対する臨床試験が行われてきた。現在、世界中で60件以上のiPS細胞の臨床試験が進行中で、その約3分の1が日本で実施されている。
ただ、実用化に際しては問題があった。病気や負傷した後、患者自身の細胞からiPS細胞を作り、それを治療に適用できるよう分化・増殖させるには時間がかかる。これだと脊髄損傷等、緊急の治療を行わないと効果がない場合や、いまにも死にそうな患者の場合には間に合わない。またオーダーメイドでの治療には莫大な費用がかかる。
このために考えられたのは、拒絶反応の原因になる、細胞表面にある抗原の種類によってヒトをいくつかのタイプに分類し、それぞれのタイプの抗原を持つヒトの細胞からiPS細胞を作ってあらかじめ大量に保管しておく、いわゆる細胞バンクを整備するという方法だった。この方法により、個々の患者に対するiPS細胞からの組織・器官の作出時間や費用は大幅に軽減し、それを用いた臨床研究も実施されてきている。
さらに最近では、拒絶反応を引き起こす抗原の遺伝子をあらかじめ除去したiPS細胞を作出し、それから組織・器官に分化させることにより、一種類のiPS細胞だけであらゆる患者に適用可能とするような試みが行われている。
これに関連して、昨年、ゲノム編集技術を用いて拒絶反応に関する遺伝子を除去したブタからの腎臓移植が行われている(第45回 初めてヒトへのブタ腎臓移植が行われる)。
4.今回の研究の手法と成果
京都大学医学部附属病院とiPS細胞研究所は、2018年~21年に、パーキンソン病患者への医薬品承認を目指した臨床試験、すなわち治験(第Ⅰ/Ⅱ相試験)(注)を行った。方法としては、健康なヒトのiPS細胞から作った神経細胞を、特殊な注射針を用いて、50歳から69歳までの患者7名の脳に500万~1000万個ずつ移植し、それぞれ2年間の経過観察を行った。
(注)臨床試験のうち、第Ⅰ相試験は少数の患者について、主に安全性や薬物状態について調べる。第Ⅱ相試験は比較的少数の患者について、有効性や安全性を検討する。第Ⅲ相試験は、多数の患者について、標準治療と比較して有効性や安全性を確認する。
通常それぞれの相の試験は独立して実施されるが、再生医療等、大規模試験が実施しにくい場合、連続する過程として、第Ⅰ相試験で用量の設定や安全性の検証を行い、その後被験者を追加して第Ⅱ相試験を実施し、併せて有効性と安全性を評価する場合もある。

今回の治験の目的は、この方法による安全性と有効性を調べることだった。
まず安全性の面では、7名全員で、移植した細胞にがん化などの異常は見られず、また重篤な副作用も見られなかった。
次に有効性の面だが、7名のうち、安全性のみを確認した1名を除く6名については有効性の評価も行われた。その結果、この6名のいずれも移植した細胞が働き、ドーパミンを出していることが分かった。このうち4名は症状や運動機能の改善が見られ、介護が不要になったり、一定期間、車椅子を使わずに生活できるようになったりする人もいた。
残る2名のうち、1名はこの治療だけでは効果が見られなかったが、薬の併用で改善した。別の1名は薬を併用しても改善しなかった。
全体としては、被験者の多くで効果が見られたことになる。特に、若く症状が軽い患者の方が、改善効果が大きいという傾向が見られた。
なお、今回の研究が掲載されたネイチャー誌には、同時に、米国とカナダを拠点とするグループによる、パーキンソン患者への臨床試験(第Ⅰ相試験)の成果も掲載された。同試験では、iPS細胞ではなくES細胞から作出された神経細胞が用いられた。平均年齢67歳の患者12名に対して投与され、18か月間の経過期間では細胞のがん化や重篤な副作用は認められなかった。また有用性に関しては、運動機能の改善が観察されたが、改善の程度は各患者で、また測定するパラメーターによって異なっていた。
ただ、両試験を通じ、少なくともこの種の幹細胞治療の安全性について確認され、また、一定の有効性は示されたと考えられる。
5.今後の幹細胞研究の展望
今回の治験で神経細胞の製造を担った住友ファーマ(株)等は実用化を目指し、今年度中にも厚生労働省に承認申請を行う方針である。認められれば公的医療保険が適用されることになる。
なおそれ以外のiPS細胞による臨床試験の状況としては、今年3月、慶應義塾大学の岡野栄之博士により、脊髄損傷患者への適用状況について報告があった。それによると、2019年から2023年にかけて4名の患者を治療し、うち、麻痺を患っていた1名が自立して立つことができるようになり、歩行を習得しつつあることが示された。また、1名は腕と脚の筋肉を動かせるが立つことはできなかった。残りの2名は大きな改善が見られなかったとのことである。
また京都大学医学部附属病院は今年4月、iPS細胞から作製した膵臓細胞を糖尿病患者に移植する臨床試験で、1例目の移植が完了したと発表した。経過は良好で、現時点では安全性に問題がないとみられる。近く2例目の移植を実施するとのことである。
これら幹細胞治療について、他国ではもっと多人数の患者で臨床試験が実施されている例もある。しかし、幹細胞治療の実用化は、他国より日本は比較的有利だと考えられる。というのは、日本では2013年に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が制定され、再生医療製品が、安全上の重大な問題がなく、有効性が期待できる場合に条件付きで承認される制度が導入されているからである。承認されると公的医療保険の対象になる。ただし、完全な臨床承認を得るためには、安全性と有効性に関するデータを継続的に収集する必要がある。
こうすれば迅速に承認がされるものの、今までの実績を見ると、必ずしもうまくはいっていない。これまでこの制度で条件付き承認を受けた4つの製品のうち、昨年、2つの製品が撤回された。一つは心臓への大腿筋細胞移植だったが、これは臨床的有用性が得られず、市販後10年近くを経て正式な承認が拒否された。もう一つは四肢の狭窄動脈の腫瘍を治癒するための遺伝子治療だったが、こちらは条件付き承認から5年後、監視データで以前の試験結果が再現されず、撤回されている。残りの2つについては、まだ有効性の確証は得られておらず、今後数年間で完全な有効性を示すことが求められる。
今後、幹細胞治療にこの制度がどの程度適用されていくか分からないが、適用対象になると公的保険の対象となるため一般の納税者に負担がかかり、議論が起こる可能性がありそうだ。
6.おわりに
iPS細胞の初の作出後20年近くが経過し、実用化に研究の焦点が移って久しいが、ようやくそのゴールが見えるものが出てきたように思われる。治療を待つ患者のためには一刻も早い実用化が望まれ、またそのための制度もあるが、上記で述べたような懸念があることも事実である。拙速による過ちを犯さぬよう、着実に一歩一歩進めていくのが近道だとも思われる。そうすることで将来的にすぐれたiPS細胞治療の市場化ラッシュにつながることを期待したい。
参考文献
・S. Mallapaty (2025), “Japan’s big bet on stem-cell therapies might soon pay off with medical breakthroughs”, Nature; Vol.640, 584-587
・(editorial),(2025), “Don’t rush promising stem-cell therapies”, Nature; Vol.640, 570
・「iPS細胞を用いたパーキンソン病治療 治験で“有効性” 京都大」(2025/4/17)NHK HP
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250417/k10014781301000.html
・「世界初、iPS細胞を用いたパーキンソン病患者への再生医療」(2020/6/23)日本医療研究開発機構(AMED)HP
https://www.amed.go.jp/pr/2018_seikasyu_04-03.html
ライフサイエンス振興財団嘱託研究員 佐藤真輔