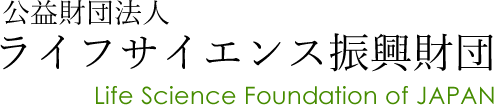第79回 遺伝子改変ブタの臓器のヒトへの移植の動向について
1.はじめに
最近、遺伝子改変を行ったブタのさまざまな臓器をヒトへ移植する研究が活発化しており、一部、臨床試験が開始されている。本ニューズレターでも何度か紹介してきたが、今回は、最近の記事等を踏まえ、これらを巡る状況について全般的にレビューを行いたい。
2.臓器移植の現状について
移植のための臓器の不足は深刻である。下の図は世界各国の臓器移植の状況を示したものである。

移植先進国の米国が圧倒的に多いように見えるが、米国でも移植用の臓器は不足している。
米国の臓器調達・移植ネットワーク(OPTN)によると、移植待機リストには本年9月現在、全米で約11万8,000人が登録され、年間約1万6千人が死後に臓器提供することで、毎年約4万件の臓器移植が行われている。だがそれでも臓器は不足しており、移植が間に合わず毎年6,000人以上が死亡している。
臓器別では最も需要が高いのが腎臓で、本年9年現在で約8万9,000人の米国人が登録され、1年間に約2万7,000件の手術が行われているものの、まだまだ不足している。
日本ではもっと深刻であり、日本臓器ネットワーク(JOT)によると、臓器移植を希望してJOTに登録している患者は本年9月現在で約1万7,000人(うち腎臓が約1万4,800人)いるが、2024年の臓器移植件数は全部合わせても583件(うち腎臓が233件)しかない。
3.臓器移植の代替法の進展(遺伝子改変ブタ以外)
(1)人工臓器
臓器移植の代替法として、まず考えられるのは人工臓器であり、著者の把握している範囲では以下のとおり。
心臓については、従来では移植を待つ間のいわゆる橋渡し治療(ブリッジ)として、又は長期間の補助を目的とした補助人工心臓(VAD)が使われてきたが、近年では埋込型の完全人工心臓も普及してきており、5年以上の延命も可能になってきている。ただ、人工心臓には駆動装置が大きいこと、ポンプ内で血栓ができやすいこと、感染症のリスクがあること等の欠点がある。
なお、阪大ではiPS細胞から作出した心筋シートを患者の心臓に貼り付けて、心臓の働きを強化することに成功している。
腎臓については、腎不全患者の治療としていわゆる透析が普及しており、広い意味では人工腎臓ではあるが、拘束時間の長さ、食事制限、合併症等の問題がある。体内に埋め込んで行うものはまだ実用化されていない。
膵臓については、インスリンポンプと持続血糖測定器(CGM)を組み合わせた「ハイブリッド・クローズドループ・システム」が、すでに海外で実用化され、国内でも2020年代中の発売が目指されている。さらに、低コストの「貼るだけ人工膵臓」の技術開発が進んでいる。
肝臓については、タンパク質、脂質、グルコースの生産等各種の役割があり、多くの酵素やホルモンの分泌や受容に関わるため完全な人工肝臓づくりは極めて困難である。
なお、慶応大学のグループは、ブタの肝臓から細胞を全て洗い流して肝臓内の骨格、血管等だけを残し、そこに細胞を充填させてバイオ人工肝臓を作る研究を行っている。
これら人工臓器は、心臓・腎臓・膵臓で5年間生存率90%超、肝臓で80%超となる通常の臓器移植に比べ、一部を除きまだまだ生存率は低い。
(2)オルガノイド
オルガノイドとは、iPS細胞等の幹細胞を培養して作製された、臓器等の構造や機能を模倣したミニ臓器のことである。従来、肝臓、腎臓、膵臓等で、本来の機能を一部持つものが作製されてきた。ただ、大きさはミニチュアサイズで、その利用目的は主に、それを用いて臓器の機能を調べたり、医薬品の効果を調べたりというものだった。
このうち肝臓については、大阪大学のグループが本年4月、iPS細胞を用いて肝臓のオルガノイドを作製したことを報告した。彼らはヒトの体が肝臓の構造を形作るうえで重要な2つの物質を見出し、それを細胞に加えて分化させたとのこと。マウスの実験で、こうして作出されたオルガノイドを複数個集めて肝不全の状態にしたマウスに移植したところ、生存率やアンモニアの分解効力が増したとのこと。
同グループは2~3年後をめどに、肝機能を補助する人工肝臓として臨床試験(治験)に入ることを目指している。
(3)ブタ工場
ヒトのES細胞やiPS細胞を、特定の臓器を作る遺伝子が欠失したブタの胚(胚盤胞期)に導入する。すると、ブタの胚はそのままではその臓器が作れないため発生が進まず仔が生まれてこないが、導入したヒト胚細胞がそれを補って代わりにその臓器に分化し、誕生したブタの仔の臓器はヒト由来になるというものである。これはブタ工場と名付けられている。
この手法により、2023年9月、中国のチームによりブタの体内でヒトの腎臓を作らせたという報告があった(第33回 中国のチームによりブタの体内でのヒトの腎臓づくりが進展)。だが実際にはできた腎臓にはまだ多くのブタの細胞が含まれており、それを改善できたという報告はない。
この方法は、もし患者自身由来のiPS細胞を用いて作出できたならば、完全に拒絶反応を除去したものとなり、究極の臓器移植になると期待されるものの、上述のようにヒト細胞にブタの細胞が混じり、特に、臓器(内胚葉由来)と由来の異なる血管(中胚葉由来)や神経(外肺葉由来)はブタの細胞のままになる可能性が高い。その意味でまだまだ解決すべき課題は多い。
4.遺伝子改変ブタの臓器移植
上記の方法に比べ、臓器移植の有力な代替法として最も注目されているのが、遺伝子改変ブタである。これは、臓器が免疫反応を引き起こすリスクを低減するため、ゲノム編集等によってブタ遺伝子の除去やヒト遺伝子の追加を行って作製したブタを用いるもので、最近、急速に進展している。
(1)心臓
遺伝子改変ブタが、ヒトで初めて移植に用いられたのは心臓である。2022年1月に米国メリーランド大学で、またその後2023年9月にもう1人の患者に、遺伝子改変ブタの心臓が移植された。彼らはいずれも、手術から2か月後に死亡した。移植した心臓が潜伏ウイルスに汚染していたことや、患者の免疫系が移植されたブタ臓器を拒絶した形跡があったことが判明した。
なおその後、遺伝子改変ブタの心臓移植が行われたという情報はない。
(2)腎臓
腎臓については、2024年3月、米国マサチューセッツ総合病院(MGH)で初めて遺伝子改変ブタの腎臓移植が行われた(第45回 初めてヒトへのブタ膵臓移植が行われる)。患者の男性は2か月で死亡した。その後何人かが腎臓移植を受けたが、そのうち最も長く生存したのは女性で、移植後4か月余りだった。
しかし、ネイチャー誌の最新の記事によると、同病院で本年1月に手術を受けた米国人男性は、術後既に6か月以上たつが、拒絶反応もなく順調だとのこと。また、それとは別の米国人男性は、今年6月の移植から3か月以上生存している。
こうした状況下で、今年になってユナイテッド・セラピューティクス社やeGenesis社は遺伝子改変ブタの腎臓移植の臨床試験の実施をFDAから承認され、実用化に向けて進められつつある。
(3)肝臓
肝臓については、2023年12月、米国ペンシルバニア大学のチームが脳死状態の患者に遺伝子改変ブタの肝臓の移植を行ったのが初めてである。遺伝子改変ブタの肝臓を患者の血管と体外で接続し、3日間脳死のまま生かし続けることができた。
また2024年3月には中国の外科医らが同様の方法で遺伝子改変ブタの肝臓を接続し、患者を10日間生かし続けることができた。
なおOrganOx社は、本年4月、FDA(食品医薬品局)から遺伝子改変したブタの肝臓移植を行う承認を得ている。
(4)肺
肺については、2024年5月、中国の広州医科大学第一付属病院のグループにより、39歳の脳死状態の男性にブタの左肺が初めて移植されたとのこと。同ブタは、中国の成都クロノガン・バイオテクノロジー社が開発した、ブタゲノムに6か所のゲノム編集を施したものだった。移植後、移植されたブタ肺には、抗体による攻撃によるダメージも見られたが、家族の要請により研究が中止されるまで9日間の間脳死状態患者の体内で生存した。
肺については、実用化はまだまだであるが、一歩は踏み出されたと思われる。
5.考察・おわりに
以上のことから、遺伝子改変ブタの臓器移植は、オルガノイドやブタ工場にはリードしていると言える。特に腎臓については、その患者数の多さと臓器不足を考えると、かなり期待されるところである。
ただ、実用化に当たっては課題がある。まず拒絶反応をいかに少なく抑えるか。特に肝臓のように各種の物質生産に関わっていると、それにより作出されたブタ由来の分子がヒトで強烈な拒絶反応を引き起こす可能性がある。またレシピエントに合った大きさの臓器をいかに用意するかも課題である。
これらについては、さらに改変する遺伝子を工夫していくことにより、また、遺伝子改変ブタのバンクを整備し、患者の大きさに合ったものを取り揃えていくことにより、解決していくことが期待される。
一方、iPS細胞の発明とその後の進展の医療に果たす役割は大きく、オルガノイド等でそれを臓器移植に適用していけば、さらに安全な方法も期待できる。
このようにいくつかの方法が並行して推進され、その成果がデータやノウハウとして共有されることにより、全体として医療の発展につながることを期待したい。
参考文献
・R. Fieldhouse (2025), “Pig lung transplanted into a person in world first”, Nature Vol.645, 20
・R. Fieldhouse, “Amazing feat’: US man still alive six months after pig kidney transplant”, (2025/9/8) Nature HP
(https://www.nature.com/articles/d41586-025-02851-w)
・OPTN (Organ Procurement & Transplantation Network) HP
(https://optn.transplant.hrsa.gov/)
・日本臓器移植ネットワーク(JOT)HP
(https://www.jotnw.or.jp/)
ライフサイエンス振興財団理事兼嘱託研究員 佐藤真輔